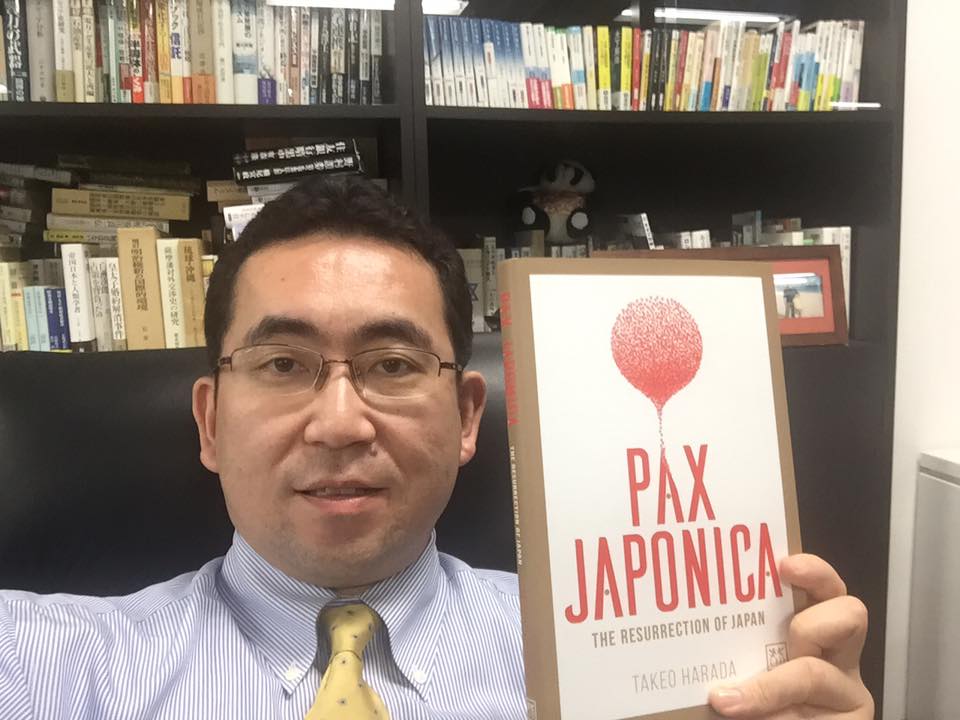我が国を統べっているのは本当は誰なのか (連載「パックス・ジャポニカへの道」)

“Bene qui latuit ,vene vixit”というラテン語の諺がある。最近、我が国におけるイノヴェーションと全世界とをつなぐ賢者から教えてもらった。「よく隠れし者、よく生きたり」という意味だ。
私たちの人生をふと振り返ってみると、結局「目立つこと」「他人より秀でて人前で褒められること」を懸命に求め続けてはいないだろうか。衣食住たりて、最後に私たちは優越感を求める。しかも他者に対する圧倒的なそれを、だ。典型的なのがマネーを求める姿勢である。飽くなき物欲も、とどのつまり、他者に対する圧倒的な優位を示すためシンボルを買い漁るためと考えれば納得がいく。
だが物事の全てに「陰陽」がある様に、人生は決して“陽”だけではないことを胸に刻み込む必要がある。そして私たちのほとんど全てが“陽”を求めて生きている(というか、日々の生活の全てが“陽”の探求といっても過言ではないだろう)分、世界のどこかで徹底して“陰”を貫いて生きている御仁がいるのである。そして私たち一人一人がほんのひとかけらの“陽”を手にして嬉々としている中、この様にして徹底して“陰”を貫いている御仁は大きな”陰“を得、それを通じて「誰も知らない水底に在りながら、そこでの微動が水面における大波を起こす」ような存在であり続けているというわけなのだ。
最近、私たち日本人は正にこのことを目の当りにした。―――怒号の中で可決された安保法制。マスメディアにおいて「支持率」の採取サンプルを巡っては依然として議論がある(無論各社共に「統計学的に厳密に裏付けられたもの」と言い切るであろうが)ということは別としても、総じてトレンドとしては明らかにこの安保法制を契機に、「第二次安倍晋三政権に対するNO」を多くの国民が付きつけ始めたことは事実なのである。
極め付けは「法の番人」である内閣法制局長官たち、あるいはそのバックボーンである我が国の「憲法学界」の“雄”たちが叛旗を翻したことであった。筆者に様に「陰」としての言論を多少なりとも生業にしている者であっても肌で感ずるのが、第2次安倍晋三政権によるマスメディア、いや規模の大小を問わずありとあらゆる「メディア」というものに対する締め付けである。様々な手段を使い、徹底して一つの方向しか流させないように動いてきた。その結果、多くの言論人たちは活路をマスメディアからインターネットへと移したが、それでも追求の手を緩めることはなかったのである。したがって多少なりとも名のある者たち、ましてや国家予算で給料を賄ってもらっている「内閣法制局長官」や、あるいは窮極においては国家予算から科研費を賄ってもらっている大学教授である「憲法学界」の“雄”たちが反論し始めるのは、相当勇気がある行為なのだ。
だが彼らは「正統性(legitimitaet)」と「合法性(legalitaet)」の違いを明確に説き始めた。我が国は国民主権の国、だから「圧倒的多数」をたまさかその瞬間に議会(国会)で占めていれば何でも決めてしまってよいという「合法性」の議論を押し通すのはまかりならないというわけである。そもそもそうした議会(国会)の行動を通常であれば許している我が国国民が憲法を決めるという行為(この点、押しつけ憲法云々という議論は誠に滑稽だ。なぜならば日本国憲法は帝国議会においてきっちりと議論され、しかも貴族院では修正までされて可決されたからだ。そして少なくとも帝国議会の衆議院については男女の普通選挙によって選ばれた議員たちによっていたことを想起願いたい)を通じて選び取ったのは根本的な価値観なのであり、それが国民主権と並んで「平和主義」なのである。この様に明らかにGHQという名の米国を意識した通説としての「8月革命説」を取らないという立場にあったとしても、それから70年間もの間、平和主義を我が国が貫いてきたという「憲法慣行」は事実として認めざるを得ないのである。そしてその根本にあったのが、「あくまでも狭い意味でも己が攻撃を受けた場合以外には絶対に武力をもって外には出ない」という個別的自衛権を墨守していたことに他ならない。
この様に書くといわゆる「改憲論者」たちが血相を変えて批判して来そうだ。しからば是非そうした方々に聴きたいのである。我が国が本気でなぜこれまでこの意味での「平和主義」の改廃のチャレンジして来なかったのであろうか。あなたたちがいう「改憲」が正しいのであれば、とっくのとうに多数派である自民党(ちなみに党綱領に「改憲」を掲げている)がそれを実現していたのではないだろうか、と。そうならなかったことには列記とした理由があるのである。無論、その理由の窮極にいるのは我が国を、そして私たち日本人を徹底して知り尽くした米国の統治リーダーたちである。
端的に言おう。―――我が国にとっての本当の「憲法」は日本国憲法ではない。「日米相互防衛援助協定(MSA協定)」である。その第1条1項前段には次のような下りがある。
「各政府は,経済の安定が国際の平和及び安全保障に欠くことができないという原則と矛盾しない限り,他方の政府に対し,及びこの協定の両署名政府が各場合に合意するその他の政府に対し,援助を供与する政府が承認することがある装備,資材,役務その他の援助を,両署名政府の間で行うべき細目取極に従つて,使用に供するものとする」
そして我が国の憲法第98条第2項は国際法遵守を謳っている。同第1項が憲法の最高法規性を謳っていることと明らかに矛盾するのであるが、この点について我が国政府はこれまで一貫して「国の存廃に関わるような条約は憲法に優先する」という態度を取り続けている。いわゆる「MSA協定」がこれをベースにして考えると、明らかに”国の存廃“に関わることは言うまでもないのである。この点、今回の安保法制を巡る議論の中で誰も的確に指摘していないようなのでこの場を借りて明確にしておきたいと思う。これが本当の意味で、「正しい憲法解釈」なのである。
さて、件のMSA協定第1条1項前段は実に含蓄のある条項だ。なぜならばこの条項に基づいて次のことがはっきりと分かるからである。
―我が国は国際平和を希求しているが、個別的自衛権の枠内にいる限り、それは実現できない。なぜならば我が国の自衛隊は「我が国」を超えて戦闘する能力を当然には持たないからだ。したがって、同盟関係にある米国にその枠外については委任し、そのサポ―トのため、ヒト・モノ・カネを当然に提供しなければならない立場に置かれている
―一方、そうした我が国による国際平和の希求は、あくまでも「経済の安定」が大前提となっている。とりわけ我が国自身におけるそれが達成出来ない時には、上述の役務・物資等提供を行わなくてもよくなる可能性がある
以上を前提とし、かつ今回の「安保法制」の成立を第2次安倍晋三政権が急いだ最大の理由が、明らかに民意にあるのではなく、対日管理を行って来た「占領国」たる米国の意向であることを前提にした場合、いくつかの重大な帰結が導かれて来ることに読者はお気づきであろうか。すなわちこうである:
―「安保法制」によって集団的自衛権を与えるということを通じて米国が我が国に求めているのは、海外での戦闘を自衛隊が当然の様に行うことが出来るようになる中、要するに武器を大量消費してくれということなのである。なぜならば今や瀕死の経済状態に陥っている米国(「シェール革命」の終焉を見れば明らかだ)にとって必要不可欠なのは、自ら見ると遠隔地にあって、独占的に米国産の兵器を大量消費してくれる国の存在だからだ。その「立ち位置」に我が国があてはめられたことをこの「安保法制」制定に向けたリクエストは意味していると解釈しなければならない
―個別的自衛権の範囲において、MSA協定に基づく我が国からの役務・物資等の提供の最たる現場となっていたのが「沖縄」なのであった。しかし辺野古の問題でこうしたスキームはいよいよ頓挫していることが明らかになり、かつそこでの事態の進展を我が国の側が止めることが出来ないこともまた明らかになったのだ。したがって米国の統治エリートたちは、この問題についてすら対処できない我が国の側に対していわば「お灸を据え」つつ、同時に窮極のプランを実施に移し始めたのである。それは「集団的自衛権」を我が国に対して認めることで、次のフェーズへと突入するということである
―次のフェーズにおいて、我が国は「交戦国」として米国産の兵器を大量消費しなければならない。南沙諸島において米中勢が”角逐“を演じ始めていることはそのせいである。2007年より誰の眼にも明らかになった金融メルトダウンの落とし前は最終的に誰かがつけなくてはならない。しかも弊研究所がこれまで繰り返し分析を提示してきているとおり、このままでは太陽活動の異変、さらにはそれに伴う気候変動の激化の影響でデフレ縮小化が全世界的に進まざるを得ないのだ。そうした時、余りにも残忍な米国勢、そして欧州勢が繰り返し用いてきた来た手段が「戦争経済(war economy)への移行」なのである。その主たる舞台はこれまで中東であった。ところがそこでの画策がうまくいかないということになれば、19世紀末から20世紀前半までそうであったように地球の表側、すなわち「東アジア」へと主戦場が変えられるというわけなのだ。この展開可能性が最終的に選択された場合、第3次世界大戦は他ならぬ我が国を含めた東アジア勢で発生することになる
「安保法制」を議論していたはずの国会議員諸兄が、全くもってここまでの認識がない(あるいはインテリジェンス機関ルートを通じた非公開情報を得ていない)ことは、彼・彼女らが形だけ繰り広げた“論戦”の底の浅さに露呈している。「その筋」のとある御仁はこの様に筆者に対して指摘してくれた:
「国会議員たちは何十パターンにもわけて、『安保法制』について議論するふりをしている。だがそこでは本質的なパターン2つが欠けていた。1つは他ならぬ米軍自身が中国人民解放軍と交戦状態に入った場合に自衛隊に対して現場での支援要請を行った場合。そしてもう1つは例えばオーストラリア軍とヴェトナム軍の部隊が共にいる時に中国人民解放軍の攻撃を受け、これに対抗するため、英国勢に支援要請を行うが、今度は英軍が我が国の自衛隊に対して支援要請を伝達してきたらどうなのか、である。これら2つのパターンこそ、今もっともあり得るというのに、国会議員諸兄たちは全く議論していない。したがっていよいよ現実に支援要請となれば、我が国の側が全くもって決断できないことは目に見えているのだ。そして我が国はいよいよ第3次世界大戦へとなし崩し的になだれ込んで行く」
それではこうした壊滅的な事態に陥る道のりの上に立って、これを阻む我が国のリーダーはいないのか。―――必ずやここでそう嘆くはずの読者に是非、今だからこそ気付いてもらいたいことがあるのだ。それは「安保法制」の制定と並んで、突然、降って湧いたように大議論となった案件が一つあったということである。それは「国立新競技場」を巡る騒動だ。
よくよく考えてみると不可思議な物事の展開であった。安倍晋三総理大臣がトップ・ダウンで決めた案件では明らかにないのである。しかもマスメディア対策には自信のある菅義偉官房長官も仕掛け人でないことが明らかなのだ。ましてや所管大臣たちや、森喜朗元総理大臣らが「白紙撤回」などという大それた決断の首謀者では全くないのである。それでは一体、どこの誰が「国費の無駄遣い」「景観破壊」を訴え、これに反対する“民の声”に答え、これら政界リーダーたちを暗黙裡に動かしたのであろうか。
その答えを知りたければ、と上述の御仁がこう教えてくれた。
「その答えを知りたければ、国立競技場が存立している土地がそもそも誰の土地であったのかを調べれば良いでしょう。要するに“我が民の声を無視した政治を行うことなかれ”というわけなのです。両陛下はここ数年、あらゆる機会をとらえて、静かに、しかししっかりと貫かれるものをもって『平和』を祈念され、動かれてきている。いよいよその御意思を踏みにじる行為に、時の総理大臣が出始めた。だからこそ、の出来事が『国立新競技場』を巡る顛末なのです」
“Bene qui latuit ,vene vixit”(よく隠れし者、よく生きたり)―――私は、以上の様な御仁の述懐を聞きながら、この言葉をあらためて胸に刻み込んでいた。我が国を統べる本当のやり方はかくのごときなのである。思い出してもみてもらいたい。11回の「マッカーサー会見」を通じて、ギリギリの外交交渉を戦勝国・米国と繰り広げたのは昭和天皇その人だったのである。そして正に臥薪嘗胆の御気持ちをもって、全ての皇室財産を差出し、現在の徹底した”陰“の世界へと入られたのである。MSA協定や日本国憲法など、全ての法規・法令がそこでの決定事項に基づくものであることは想像に全く難くないのである。
そしてそこでの御想いはMSA協定のこの一語に尽くされている。―――「経済の安定」、そう乱高下することなく、”中庸“を保っている状況こそ、全ての安寧の起源なのである。だからこそ、莫大な量の簿外資産も含め、「全てを供出」ということになったのである。原子爆弾という残酷無比な兵器まで用いる米国をも経済的には飲み込みながら、不死鳥のように甦るためである。他方、米国勢はといえば、戦前からの緻密な研究に基づき、我が国国民は豊かでさえあれば、決して牙を剥かないことを知っていた。だからこそ、このMSA協定に署名したのである。
だが、時は流れ、その「記憶」は確実に薄れていった。表向きは民主主義のルールによって選ばれるものの、その実、こうした微妙な均衡点(陛下と米国勢の統治エリートたちとの間における)を保つことの「代官」として選ばれるに過ぎない内閣総理大臣が、いよいよ暴走し始めたのである。我が国の本当の主は米国だ、とばかりに、直接それと交渉しようとした。その結果が「安保法制」を巡る暴走なのである。見かねた我が国の本当の「権力の中心」が、正に「葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国」(柿本人麻呂)において正統なやり方でその御意思を決然と、しかし”陰”のやり方で示された。それが「国立新競技場」を巡る顛末の実態なのである。
米国勢はこうした事態の展開をやや呆れ顔で内心見ているようだ。彼らとすれば正直、安倍晋三総理大臣には「もっとうまくやって欲しかった」である。静かに、しかし着実に「安保法制」を法制度化してくれればそれでよかったのだ。ところがここまでの騒動になってしまい、さらには多くの若者たちに「日本国憲法って何だ?」と火をつけてしまった。「そろそろ選手交代か」と思わざるを得ないのにも、米国勢の側において充分な理由があるというわけなのだ。
他方、今回の顛末で決定的となったのが我が国の本当の「権力の中心」の所在と、その御意思である。時の内閣総理大臣が”白紙撤回“を、しかも何か見えない力を心底怯えるかの様にせざるをえなかったのである。そして「安保法制」という我が国の上述の意味での(ギリギリの外交交渉の結果としての)平和主義を根底から覆す法令の制定を巡る騒動のクライマックスにおいて、この”白紙撤回“がなされたことも記憶にとどめておきたい。二つの出来事は「偶然」ではないのである。「必然」なのだ。そこで示された御意思はただ一つ。「平和を貫け」―――この一点なのである。
最終的にこの御意思を遂げられるには、1945年8月15日という「あの夏の熱い日」以降続けられたギリギリの対米交渉の”続き“をされなければならないのである。普通であれば、米国の側にその様な敗戦国との再交渉に応じる気などさらさらないのである。しかし、やり方がたった一つだけあるのだ。しかも言挙げなどせず、かつ“Bene qui latuit ,vene vixit”の大原則をあくまでも貫くやり方である。
これでお分かり頂けただろうか。我が国が“デフォルト(国家債務不履行)”へとそう遠からず陥ることの理由は正にここにあるのである。「そうなる」のではなく、「そうする」のである。これまで70年間にわたって我が国を押さえつけてきたあらゆるフレームワークから己を解き放ち、「平和」という至高の大義を掲げながら国際社会全体を導いていく。そのためには必ずそうしなければならないのである。さもないと我が国を残虐非道な第3次世界大戦へと引きずり込もうと今や画策し始めた米国勢を交渉テーブルにつけさせることは不可能なのだ。
御方の御意思は神宮の森で示された。あとは私たち国民が「日本国民」であるが故に、それに従うのか、あるいは窮極において「日本国民ではない」が故に、これを無視するか、そのいずれかなのだ。この意味での「本当の闘い」に私は身を引き続き投じていきたいと思う。なぜならばそれこそが、ヒトとして生を受け、前に進むべき本当の道なのであるから。
2015年7月19日 東京・仙石山にて
原田 武夫記す