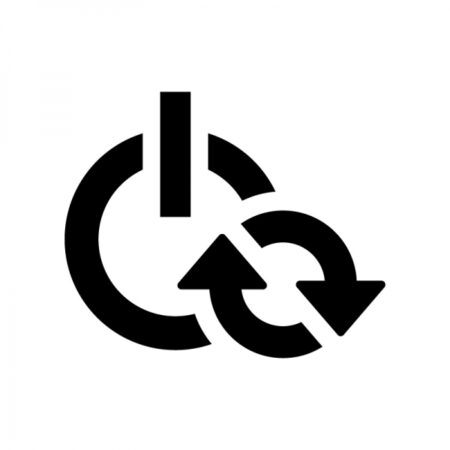夏の北京と谷崎潤一郎、そして「赤い貴族」の話。(原田武夫の”Future Predicts”. Vol. 48)
この3日間、実に7年ぶりに中国の首都・北京を訪問してきた。我が国では酷暑、酷暑と騒がしいが、彼の地もまた同じであった。ただ、その前日まで大雨であったとのことであり、心なしか陽気の違いを感じた。
そうした中、旅のお供として携えていったのが作家・谷崎潤一郎の文庫本だ。最近、訳あって『細雪』を読んでいる。つい先日まで、全くもって興味すら湧かなかったこの作品だが、この数週間かけてじっくり味読している。そこで延々と独特の文体で描かれる「蒔岡家の4姉妹」の姿は時に優雅であり、また時には冗長だ。しかしだからこそ、これまでには感じたことのない「何か」が読む者の脳裏にひらめくのだから実に不思議な作品だ。今回も1冊はこの作品『細雪』の下巻(KADOKAWA)を携えていった。
そしてもう一つ、谷崎潤一郎の作品を持って行った。『陰翳礼讃』だ。こちらの方はエッセイ集でありどちらかというと勝手気まま、谷崎自身の独断と偏見をそのまま綴ったといった方が良い作品である。中公文庫の装丁はかなりきっちりとしたものであり、読む者の心は不思議と「そういう作品であるはず」とついついなってしまうのだから不思議だ。しかし、北京へと向かうJAL便の中で、こんな一節をこの本の中に見つけ、思わず噴き出してしまった。
思うにこう云う不潔と不規律とは、何時の時代を問わず支那人には免るべからざる通有性であって、どんな進歩した科学的設備が移入されようとも、一とたび彼等の経営に委ねられれば、忽ちそれが支那人独特の「物臭さ」を帯び、折角の近代的な尖鋭な利器が東洋風な鈍重な物に化してしまう。清潔と整頓とを文化の第一条件とするアメリカ人なぞの眼からは、許すべからざる無精とも見られるであろうが、支那人自身はちっとやそっとの不都合はあっても、用さえ足りれば済まして置くと云った風な、伝統的な性癖を容易に改める様子もない。そして時に依っては、西洋人の極端な規則ずくめと神経質とをうるさがるような気味合いも見える。欧米流の礼儀作法とし云えば事毎に反感を寄せ、自分の国の風習なら一夫多妻の精度をさえ是認していた晩年の辜鴻銘翁なぞは、定めしこんな事象に対しても相当の意見があったであろう。
「中国といえば不潔と不規律」とは、かくいう谷崎潤一郎だけが持つ偏見ではなかろう。いや、事実、時に中国の街を歩くと実に不潔と不規律に出くわすことがあり、当惑することしばしである。だからこそ、私たち日本勢はというと、時に中国人を馬鹿にし、偏見の色眼鏡を持って見続けることとなる。谷崎潤一郎はというと、こうした中国勢(彼の時代でいう「支那人」)との比較において、日本人は優位であるかの様な描写に終始し、そこに時代を感じてしまうのは私たけであろうか。北京の上空にちょうど差し掛かると『陰翳礼讃』を読み終えた私は人知れず、気まずさを覚え始めていたが、そうした中でJAL機は予定どおりに着陸をし、広大な北京首都空港へと滑り込んでいったのであった。
北京ではここに来て数年来のカウンターパートである「赤い貴族」氏と面会した。これまでは東京での面会がもっぱらであったが、今回はかねてからの誘いに応じる形で北京を訪らうことにした。すると阿吽の呼吸で「赤い貴族」氏からは、市内有数の高級住宅街の中にある同氏個人宅で食事にも招待するから是非来てほしいとご招待頂いた。やや気後れしたことをここでは吐露しておきたいが、結果として訪れて見れば「会談」すること5時間、実によくしゃべり尽くした。
今回の「会談」に際しては、国務院からも高官が同席してくれていた。「中国国内のことならば彼女に何でも聞いてくれ。政治局の主要文書をドラフティングしているから何でも応えられるはずだ」と言われた同女史の年齢はというと、恐らく還暦をやや過ぎたくらいであろうか。頭脳明晰な方であったが、一言話し始めると正に「大演説」であり、5分、10分と私たちは全員、その場で同女史からの御高説を拝聴することとなった。これもまた、暑い夏の北京における佳き思い出といったところだろうか。
その内容は余りにも機微にわたるものであったため、ここでは残念ながら全貌を語ることは出来ないことをお赦し願いたい。しかし一言だけ述べるならば、上述の様な谷崎潤一郎ばりの「偏見」は物の見事に打ち壊されたといったところであろうか。誰の口から、とはあえて言わないが、こんな言葉が飛び出した時、聴いている側の私は正直、自らの耳ですら疑わざるを得なかったことを吐露しておきたい。
これはあくまでも私見だが。「ウクライナ戦争」ではロシアには負けてもらいたいと思っている。
あるいはこんな言葉も飛び出した。
中国が今、香港を舞台にして推し進めているRWA(Real World Asset)政策は、とどのつまり、中央銀行というシステムそのものを消し去ってしまうかもしれない。
「不潔と不規律」といった偏見とは全く相容れないこうした言葉を「赤い貴族」氏の邸宅で耳にした私は、その衝撃に独りでは耐えられず、旧知の先輩・同輩同僚たちが詰めている在中国日本国大使館に、事実上、アポ無しで押しかけることにした。実にアポ成立の2時間前の申し入れだというのに、ここ数年前に新設したという真新しい大使館脇の大使公邸で、金杉憲治・特命全権大使(筆者より8期上)と横地晃・次席公使(筆者と同輩)が忙しい公務の合間を縫って会ってくれた。同大使からは「これからはいきなり来るのではなく、事前に連絡をくれ」と笑顔で釘を刺されたが、その言葉を聞いた時、かつて『アンネの日記』の著者アンネ・フランクがその父と共にアムステルダムの隠れ家から連行される時、その任に当たったドイツ兵たちが父の飾っていた第一次世界大戦従軍時に獲得した勲章に対して、静かに敬礼したという下りを、私は思い出していた。「自主退職」したというのに、厚遇してくれた皆様には心から重ねて感謝を申し上げたいと思う。
「赤い貴族」氏は決していわゆる「政府要人」ではない。しかしその発言は明らかに「党中央」のラインを明確に踏まえたものであり、絶やさない笑顔の向こう側に、この大陸を統べる者たちの堂々たる姿勢をあらためて垣間見た次第だ。そしてまたその発想は極めて先進的であり、論理的でもある。それに比べれば我が方が壊れたラジオの様に掲げる「戦略的互恵関係」などというタームは余りにも陳腐であり、意味がないと強く感じた。むしろ、全てが流動化の一途を辿っている今だからこそ、共に利を上げつつあるように見えて、相手の尻尾をつかんでいるといったような、良い意味での手練手管、戦略に戦術が、大いなるマネーの臭いと共に必要だと感じた次第である。
「あの通りの向こう側にあるのが、貴代表が投宿しているホテルでしょう?そのちょうど間にあるのが”中南海”ですよ」
そう教えてくれた「赤い貴族」氏からたくさんの宿題が事実上降ってきた感があった今回の北京行きだったが、今、独り東京で静かにそれを頭の中で整理している。時代は着実に動いている。『細雪』の美に耽溺している暇は、もう無いのかも、しれない。
2025年8月2日 台風明けの東京の寓居にて
株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 ファウンダー/代表取締役会長CEO/グローバルAIストラテジスト
原田 武夫記す
・・・
いかがでしたでしょうか?「この後何が本当は起きるのか?」についてご関心のある方は是非、音声レポート「週刊・原田武夫」最新号(2025年7月30日リリース)をこちらからお聞きくださいませ(クリックするとご案内ページにジャンプします)。