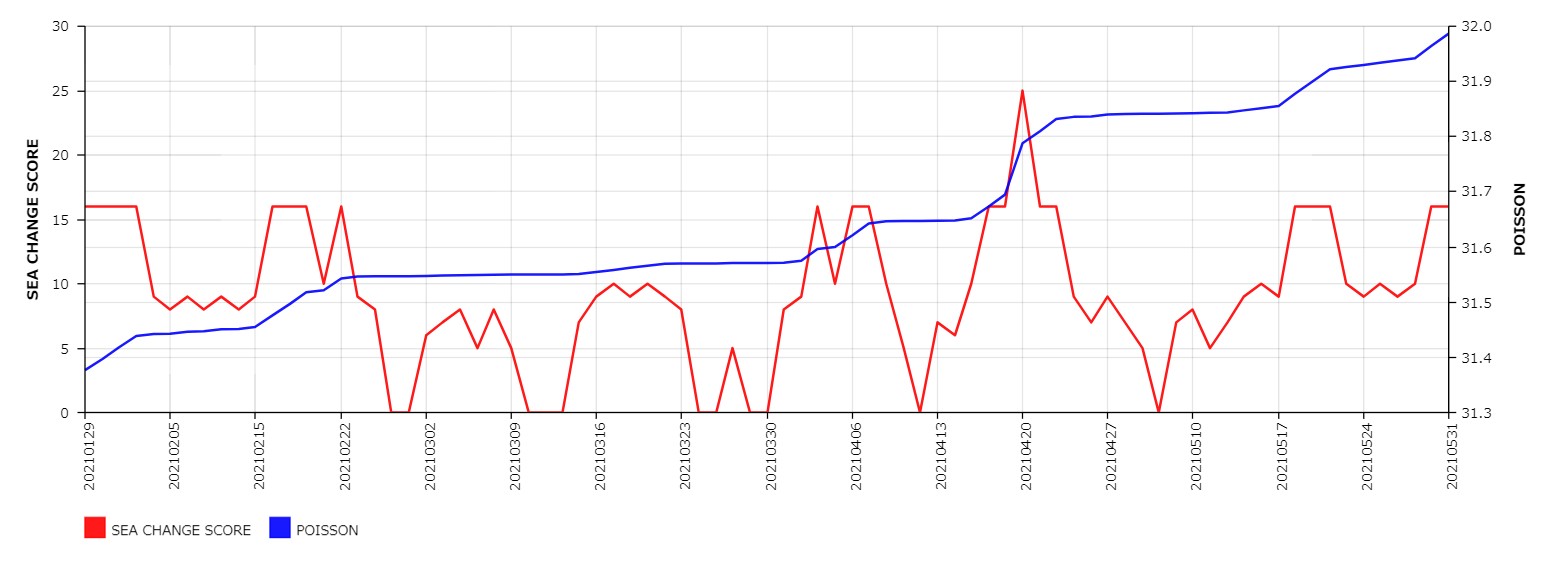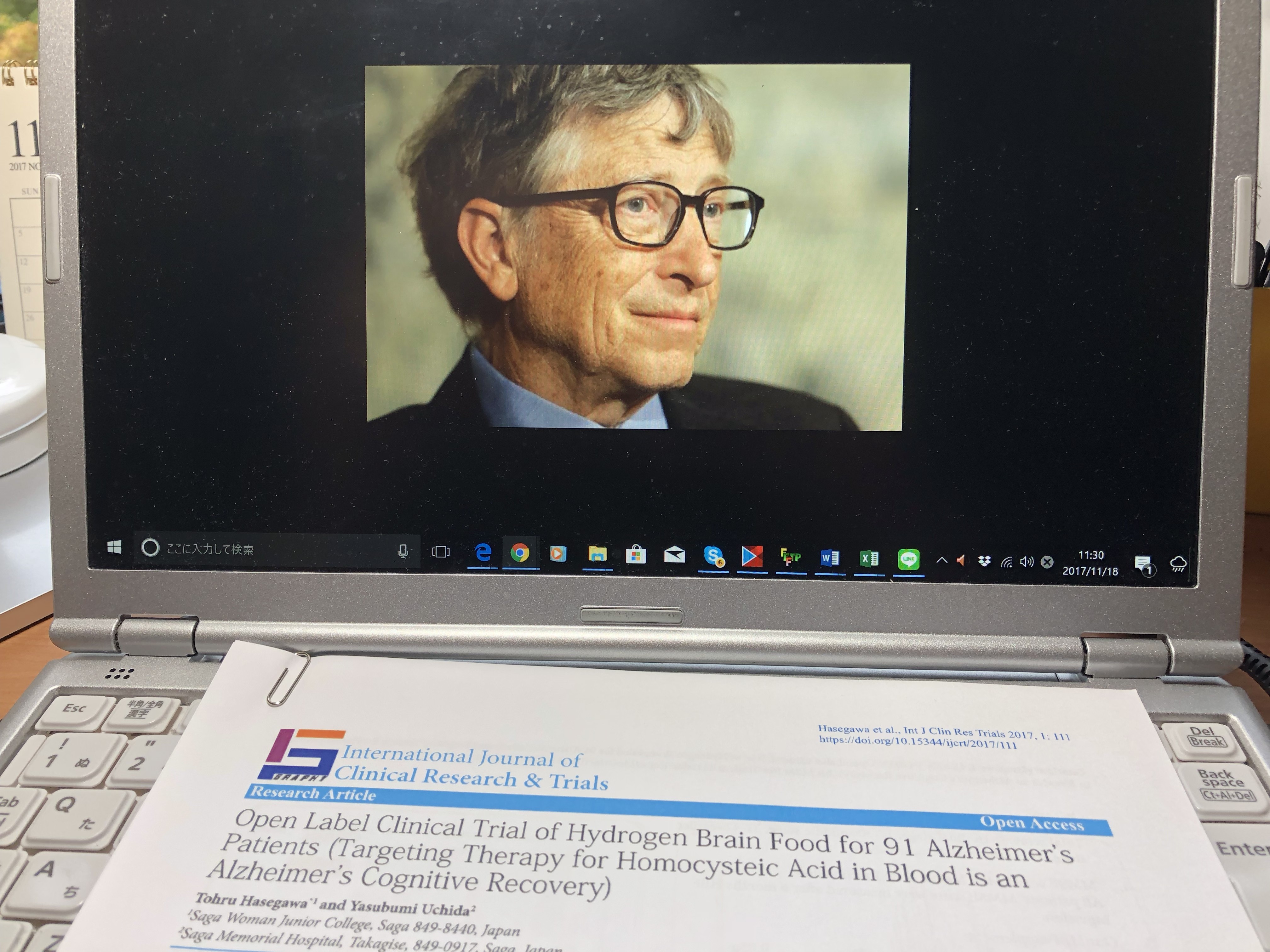スイス・フラン急騰と巨額損失 それでも資本主義は終わらない (連載「パックス・ジャポニカへの道」)

15日(チューリッヒ時間)、スイスの中央銀行である国立銀行がスイス・フランの対ユーロ上限額を撤廃する旨の政策変更を公表したことがその後も大きなインパクトを国際社会全体に対して与え続けている。時間が経つにつれ、ここかしこで数多くの「越境する投資主体」たちがもはや巨額の損失をリカヴァー出来ないことが判明。「破綻」を宣言するに至っている。
この様な状況になると必ずこう言い出す評論家たちがいる(ちなみにここでいう「評論家」とは、当研究所の様に「未来」についてあらかじめ語るのではなく、あくまでも起きてしまった「過去」について後付けで語る向きのことを指している)。
「資本主義は終わった。そもそもそのシステムには問題があったのであり、それによって生じた格差を即刻是正すべきだ」
かつての「左翼陣営」に属していた評論家たちにはこういった向きが多い。「それみたことか、やっぱり米国は間違いだったじゃないか」というわけである。1989年にベルリンの壁が崩壊し、それと相前後してフランシス・フクヤマが著作「歴史の終わり」を発表。「左翼陣営」が完全なる敗北を喫したことをもって資本主義・自由主義を奉ずる西側(=米国流)システムが勝利したと高らかに宣言したわけである。その時に感じたルサンチマンを「左翼陣営」の評論家たちは一斉に放出している感がする。
だが、彼らは決して薄々感じている真実を言おうとはしないのである。つまり「格差に苦しんでいる読者層に対して自らの本を売りつけ、ベストセラー作家になって荒稼ぎをすることが、実は形を変えた『貧困ビジネス』に過ぎないということ」を。彼らの巧妙な罠にはまってはならない。なぜならば言論でしか食べていけなくなった彼らはなぜそうなったのかといえば、往々にして学生運動にのめり込んだ経歴を持っているからだ。その際のすさまじい人心操作・圧迫、いわゆる「オルグ」からすれば、こうした書籍やメディアを通じた大衆扇動など大したことではないのである。こうした過去を決して公言せず「異能の人」などと言われている作家の著作を盲目的に買い集め、その言葉を盲信している読者たちが不憫でならない。
最近流行りの米欧発の書籍についても全く同じことが言える。母国フランスでは「??」とされているが、不思議と米英ではもてはやされ、我が国に輸入されたという経緯を持つトマ・ピケティによる「21世紀の資本」がその典型だ。簡単にいうと「資本収益率は経済成長率を上回る。だから所得の不平等が生じるのであって、これを是正すべきだ」というのがその主張なのである。
今、我が国では明らかに所得格差が拡大しつつある。そのような中で「誰が悪者なのか」という議論がマスメディアを通じて煽り立てられるのには理由がある。それは先ほどの「異能の人」ではないが、要するに多くのメディアの受け取り手(=読者、視聴者等)をその議論の「消費者」にすることが出来るからだ。ただでさえ不況にあえぐ出版メディアは「これだ!」となったらばその解説本やら、ムック本やらを大量に刷り始める。先ほどの「21世紀の資本」についても全く同じであり、一体どこから湧いてきたのかと思う位の量の「ピケティ本」が我が国では氾濫している。明らかに「異常」である。
はっきり言っておこう。資本主義は終わることはない、のである。
なぜならばこれまでの人類史を見る限り、資本主義には次の3つのタイプがあったからだ:
●産業資本主義:モノをつくってそれをより多くのお客様に売る、そのための優れた製品・システムを造る
●金融資本主義:時間の経過による利子の増加を前提に、カネがカネを呼ぶ仕組みを中心に据える
●民族資本主義:諸国民間で格差が生じることを前提に、民族国家が外部との障壁を造り、自らを護る仕組み
そして今、生じているのはこの2番目のタイプの資本主義である「金融資本主義」が終わるということに過ぎないのである。逆に言うならば(元来の資本主義である)産業資本主義と民族資本主義という意味での資本主義はそれによっては終わらないのである。
もっというならば「21世紀の資本」が突然流行った(ようになぜか米英から見せかけられている)理由もここにあると見るべきなのだ。彼らはあらかじめ知っている、「終わるのは金融資本主義だけだ」ということを。しかしだからこそ次のゲームにおける序盤戦で自らがポール・ポジションをとるべく、「資本主義全体が終わりを告げる」かのように大騒ぎをしているというわけなのである。私たち日本人は早くそのことに気付かなければならない。
事実、ここに来て生じているのはまず、民族資本主義という意味での資本主義の興隆なのである。中国、そしてロシアを見ればそのことはすぐに分かる。あれだけ米国から「経済・金融制裁」で痛めつけられても徹底防戦していることの本質は、二つの異なる資本主義のぶつかり合いだったとういわけなのである。今、原油価格の崩落をビナイン・ネグレクト(beneign neglect 意図的な無視)しているサウジアラビアを筆頭としたアラブ諸国もまた同じなのである。彼らは金融資本主義がもたらしたもろもろの矛盾の解決を「イスラムの恐怖」に押し付けようとする意図が見え見えの米欧に対して「NO」を突き付けているのである。言ってみれば「アラブ民族資本主義」だというわけなのだ。
産業資本主義ということで言うならば、実のところ「モノづくり」に回帰しているのは、何を隠そう、金融資本主義の総本山として(表向きは)君臨してきたはずの米国なのである。それが証拠に本来ならば1960~70年代に我が国で発展した様々な発想法(KJ法など)を今更ながら「デザイン思考(design thinking)」などと称し、自らが本家本元であると主張し始めるのと同時に、1997年には「才能獲得の戦争(The War for Talent)」をマッキンゼー&Co.を筆頭に主張し始め、世界中から人狩りを始めたというわけなのである。その一方で「アウトソーシングこそ、これからのモノづくりの基本だ」と言いながら世界中のモノづくり企業にそれぞれの国々から生産拠点を移すよう推奨しつつ、その実、自らは結果的に米国内へと生産拠点を戻した。それと同時にチャールズ・ハンディが提唱していた「シャムロック型組織」を地で行くような企業(例えばGoogle, Microsoftなど)を林立させ、「24時間ビジネス・モデルを考えるのが好きで好きでたまらない若者たち」を世界中から集めてはそこに収容し、馬車馬のように働かせ続けているのである。これらの現実に起きている現象を見れば、金融資本主義の「総本山」である米国こそ、その実、その限界に気付いていたことは明らかなのであって、「その次」に向けて着々と地歩を固めてきたというわけなのだ。
「金融資本主義の終焉と、産業資本主義+民族資本主義による勝利への道」―――これこそが、今起きている世界の現実なのである。そして我が国の経済回復プログラムも、こうした大道に沿った形で、いやむしろそれを率先垂範する形で推し進められるべきなのである。なぜか。
その理由は簡単だ。「産業資本主義+民族資本主義」というタイプでの資本主義で最も成功したのは、他ならぬ我が国だからである。思い出しても見て頂きたい。明治維新の頃、「富国強兵」といって殖産興業策をとった際、我が国が着手したのは「金融システムの整備」「金融商品の拡充」だったであろうか。全くそうではなく「産業」、すなわち「モノづくり」だったのである。
しかも戦前期の我が国における資本主義の中心には明らかに「天皇」「皇室」が存在していたのである。それが証拠に、第二次世界大戦において敗戦した直後、このシステムを解体すべく我が国にやってきたGHQという名の米国が目にしたもの。それは「4大財閥の実に10倍以上の資産を持っている」天皇家という実態だったのである。驚いたGHQ(米国)が直ちにこれを解体し、二度と天皇家が「産業資本主義+民族資本主義」の音頭取りを我が国で出来ないよう、用意周到に二重三重の策を講じたことは言うまでもない(日本国憲法第8条「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」)。
なぜ我が国が「産業資本主義+民族資本主義」へと明治維新以降、移行することが出来たのかといえば、徳川幕府による江戸時代の経済運営が正にそうだったからである。「鎖国」とは形を変えた民族資本主義であり、かつそこでは金融資本主義は発達しなかった。なぜならば多少のブレはあるにせよ、貨幣は必ず実体としての価値とみなされていた「金・銀」の裏付けを必要としていたからである。したがって「時が経てば利子がついて儲かる」などということはありえず(なぜならば貨幣量には限界があるため、インフレにも限界があらかじめ設定されている。利子による儲けにも当然限界がある)、よって人々は総じて(適度な)デフレ経済の下、カネではななくモノへと関心を集中させていたのである。当然、その裏側にあるのは、「働いた分だけ=価値を創出した分だけモノを得ることが出来る」というシステムが機能していたことになる。これこそ、正に「労働価値説」なのであって、マルクスが語る理想郷は実のところ、ある意味、我が国では17世紀から実現したというわけなのだ。
「時が経てば利子がついて儲かる」という金融資本主義が機能しない以上、人々はその意味での「時間感覚」を持たずに暮らすようになる。つまり古代ギリシアの用語でいうならば、「過去から現在、そして未来へ」という意味での時間感覚であるクロノス(kronos)ではなく、「常に充実した今」という意味での時間感覚であるカイロス(kairos)しか、そこでは持たれなくなるのである。
そうした、現在の金融資本主義における強迫観念そのもののような時間感覚(クロノス)とは全く違う時間感覚(カイロス)が社会に広まるとどうなるかといえば、人々は細密な世界、微小な世界へと関心を寄せるようになってくるのである。江戸時代のすぐれた手工芸品の数々を思い起こせばそのことは一目瞭然だ。いやもっといえば古来、そうした伝統を粛々と保ち、それをそのまま保蔵したのが「京都」という街なのである。今、世界中から依然にもまして外国人たちが「KYOTO」に飛来している背景には、こうした一連の流れと伝統があることを私たち日本人は認識しなければならないのだ。
これから崩れる金融資本主義という名の残骸の向こう側に見え始めた世界が「産業資本主義+民族資本主義」というイメージであるからこそ、我が国は世界史の中心に立ち、それを動かす立場に置かれるというわけなのである。つまりパックス・ジャポニカ(Pax Japonica. 日本の平和)の本質とは、この意味での資本主義の時代への移行なのであり、かつ刹那的な時間という意味での「クロノス」ではなく、永続的に充実した時間という意味での「カイロス」への移行にこそあるというべきなのである。そしてそこでは強迫観念にかられつつ富を集積することが自己目的化したシステムではないため、ついには「人命の消費・商品化」としての戦争経済にまで手を出し、何とか世界史を廻そうなどということは全く不要になってくる。パックス・ジャポニカがなぜ平和に満ち溢れた世界になるのかといえば、そこに理由があるのだ。
そしてこれは何よりも、「自らが全うに働き、価値を創出した分だけ、モノを得ることが出来る」というわけなのだから、まずはその意味での形ある自己実現こそが人間社会の基盤に置かれる世界の始まりでもある。「格差」などという議論はそこでは消失する。なぜならば生まれながらにしてハンディキャップを負った方々への救済は別とすれば、要するに自らが得ることが無いのは自らが努力していないから、という余りにも単純な帰責の方程式がそこでは(再び)「常識」となるからである。
私・原田武夫はこの1月、世界の有力20か国の集まりであるG20を支えるべく、グローバル・カンパニーのCEOたちが寄り集い、グローバル・ガヴァナンスのためのアジェンダを設定する「B20」に参加することが決まった。今年(2015年)の議長国であるトルコから、先般その旨の正式通知を得たばかりであり、これから始まる2月以降、頻繁に出向いていってはそこでの議論に積極的に参加する役割を負っていくことになる。B20が提示したアジェンダの実に3分の1がG20の各国首脳が採択するグローバル・アジェンダに採用され、「世界のルール」になっていくのだという。
私はまずはこのB20の場において、我が国を代表する一人として、以上の意味での世界史的な大転換について語ると共に「在るべき方向」を世界中の人々に対して示していければと考えている。もはや時代は嘆息していることなど許さないのである。ましてや狭い国内で内輪もめをしている暇など全くないのだ。
「今起きていることが世界史的な転換であり、その先にあるのはパックス・ジャポニカであるということ」
このことを、私とIISIAは諸国民に対して高らかに謳い、協働を促していく。
2015年1月18日 東京・国立にて
原田武夫記す
(以上)