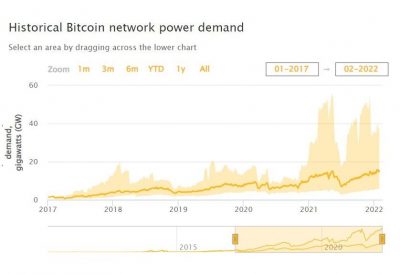器と中身が合わない時にどうするべきなのか (連載「パックス・ジャポニカへの道」)

「縁(えにし)」という言葉ある。己の前後、左右を見渡すと、空間にせよ時間にせよ、何者かに連なっているということだ。その連なりを意識する時、私たちは「意味」をそこに見出すことになる。縁(えにし)とは「意味」の連鎖である。その「意味」を辿っていく先に何が己のことを待ち受けているのかと思うと、たまらなく楽しくなってくる。
己が何故に生を受けたのか、その「使命」を悟って前に進む人物。そうした人物のことをヒトという。これに対して、その意味での知命の瞬間が来ず、ただひたすら何者かを誹り、それでいながら己は何もしようとしない者のことを、ヒトとヒトの間を漂っているという意味で人間、という。同じ人類であるとはいっても、この世には二種類の者がいる。ヒトと人間。この間には越えがたい溝がある。
一番厄介なのは、器、すなわち容姿からすると男女を問わず端麗なのだが、しかし中身はどうにもこうにも知命とは言い難いレヴェルの人物である。己に宿った「宿命」を知り、しかしそれを己の意識をもって受け取るか、あるいは拒み新たな命(めい)を掴み取るか、そのずれかをするという意味での「運命」を体得したことのある者ではないわけだ。この意味でのヒトは老若男女を問わず、実に佳い顔をしている。端的に言えば元気(「気」の「元」=発信源)なのであって、自ずから多くの人物が寄り集ってくることになる。人脈の交差点となり、そこに行き交う「情報」がやがて新たな価値を生むようになり、そのヒトはますます尊ばれ、周囲はそれに触れることで得る幸福の対価を支払うようになる。したがってこの手のヒトは決まって、大富豪とまでは行かずとも豊かな生活を過ごしている。そのことがまた、落ち着いて「知命」への旅を歩ませることへとつながり、ますます磨かれていく。
器と中身が違う人物についてはどうか。一見すると器は光り輝いている。年齢は問わず、光るものを持っている眼差しをしているのである。あるいは群衆の中にあっても、すぐに他と区別できるような、そんな顔つきをしているし、背格好もしている。実際に口を聴いてみると、確かにそれらしいことを言う。時には「若いのにしっかりしている」ということにもなる。
だがどうにもこうにも、「縁(えにし)」というものが分からないのである。己の固い殻に閉じこもり、目の前に出会う全ての事共、人物たちに対して、それとの邂逅に宿る「意味」を探ろうとする姿勢が一切見られない。さりとて、自己を振り返って器を磨くというわけでもないのである。ただただ野放図な生き方をしているのである。ヒトである立場からすると実にもったいないと思ってしまう。だからこそ、手を差し伸べるのである。「縁(えにし)」を悟るように導きたいと強く想ってしまうのである。
すると、である。今度はとてつもないことが大抵の場合起きてしまう。少しだけ触れると電気を放ち、周りを蹴散らかす電気ウナギのように突然、威嚇し始めるのである。パターンはいつも同じなのであって、現代社会においては「規制緩和=完全自由化」というイデオロギーの裏側に仕込まれた「何かあったらば法的紛争に持ち込めば良い」という、司法マフィアたちのビジネス・モデルへと逃げ込むのが常套手段だ。そこまでいかずとも、とにかく誰が決めたか分からないルールを杓子定規に突然掲げ、それに反している、ハラスメントだと大声で叫び始めるのである。野次馬というのは常にいるのであって、そうした騒ぎが起きると今やソーシャル・メディアという拡声器を持った小人(「人間」)たちはやいのやいのと集まり、これをはやし立てることになる。その結果、ここで生じるべき「縁(えにし)」は立ち消えてしまう。いや、そもそも強烈に負の「縁(えにし)」であったという風に整理されて終わってしまうのである。
想うに「昭和」までの我が国は「縁(えにし)」の世界であった。そもそも出会いというものが現在からすると遥かに希少であったため、「出会うこと」についての”意味“を人々は真剣に考え、悩み、喜び、そして分かち合って来た。それはスローモーなものであったかもしれないけれども、思念に満ちたものであり、それだけ幸福という意味での充実に満ち溢れていたように思う。
だが今は違う。とりわけ若い世代は先ほど述べたイデオロギーに完全に毒されてしまっている。ほんの一部の、いわゆる「厳しい親」、すなわち「昭和」までの我が国におけるヒトの在り方について徹底して躾てくれる両親の下で育った者たちを除き、生まれた時から中身が腐るような、したがってヒトには永遠に成ることが出来ず、ただただ漂う「人間」として生きることを余儀なくされている不幸な自分に気付かないような、そうした生を送らされているのである。もがけばもがくほど、規制緩和=完全自由化の世界、しかもグローバル化で国境が無いので実に様々な「出会い」があるのである。だがその度に「縁(えにし)」をどの様に処するのか分からないから、この手の若者たちはハレーションばかりを続出させていくことになり、何とも満たされないまま、ただただ漂い続けることになる。
先日、師から強く諭された。
「使命を持って生まれていない者に、使命を持って生まれた者と同じ教えを施してはならない。なぜならば使命を持って生まれていない者は、試練に耐えることが出来ないからだ。ただただ、枠組みを与え、その中で生きさらばえてもらえばそれで良いのである。これに対して使命を持って生まれたものには、次々に試練が待っている。だがそれを乗り越える度に報償が訪れることになる。もっともそれに甘んじではならない。あえてこれに安住することなく、更に己の使命に向かって突き進むことにより、更に大きな試練に立ち向かうことになる」
この師の言葉の延長線上で考えるならば、ヒトがここでいう「器と中身がずれている者」に出会い、しばし困難に直面することになるのは、一つの試練ということになるのであろう。しかしそこで我執することなく、あるべきことを貫くと不思議とこの意味での試練は解消され、次へと進む道が開けて来ることになる。
我が師はその意味で「無情であれ」と繰り返し諭して下さる。仮に己の使命を果たしたいというのであれば、審神者(さにわ)になれとも教えて下さる。「神」とは、結局のところ私たち人類の思念が創り上げたものに過ぎない。したがってそこに宿っている「神」をいかにとらえ、処するのかも、結局は私たち自身の思念に依っているというのが正しいのだ。その意味で「器と中身が合わない者」を目の当りにしても、それに憐憫をかけ、拘ることなく、己の使命を果たすために与えられた尊い時間を一分一秒たりとも無駄に費やすことなどせず、前進すべきなのである。なぜならば「器と中身の会わない者」はいってみれば鬼神なのであるから。本来ならば崇高な道を「縁(えにし)」によって導かれながら歩むかもしれなかったかもしれないが、持って生まれた何かによってそれを遮られている、その意味で哀しい存在なのである。神でありつつ、鬼であることもやめられない。そういった輩だからだ。
これまでそうであったように、これからもまた私は、己の使命が果たされた瞬間を求める道を驀進する中で、数多くのこうした小さな鬼神たちに出会っていくことになるだろう。それがまた試練となる時もあるやもしれない。だが、己の使命へと連なる「縁(えにし)」は何物にも勝る強さなのであって、必ずやそこへと至る道は切り開かれ、鬼神たちは去ることを余儀なくされていく。
いと畏きはこの「縁(えにし)」なのである。それが一体何であるのか。求道は続く。
2016年1月24日 東京・仙石山にて
原田 武夫記す