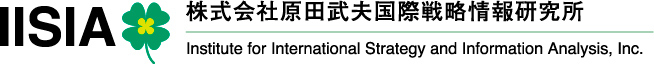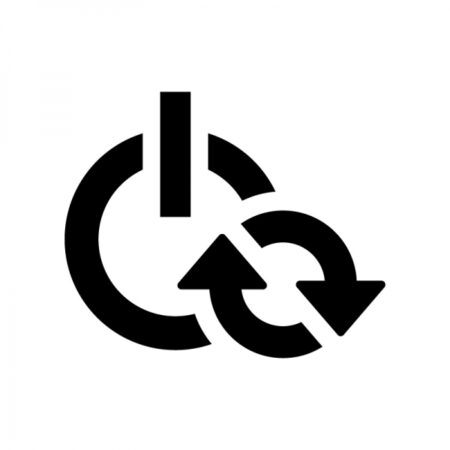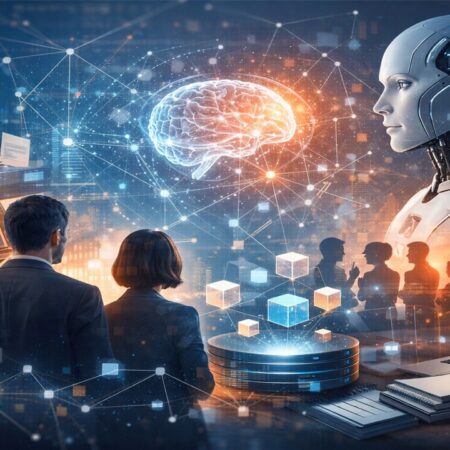Artと、Technologyと、Entrepreneurshipと。(原田武夫の”Future Predicts”. Vol. 30)
昨日(15日)、岡山大学津島キャンパスで開催されたPSI(Peace & Sceience Innovation)主催の学生ピッチコンテストに審査員として出席した。このPSIとは、広島大学を中心とした中四国の様々な大学がコンソーシャムを結成し、所属する学生たちによるアントレプレナーシップを推進するフレームワークである。弊研究所はご縁あって、昨年(2024年)よりこのフレームワークに参画させて頂いている。
12人の選抜された学生たちによるピッチが実施され、それぞれ、それぞれなりに考え抜いた感のある起業アイデアが現場では提示された。私はというと、まずは講評の担当とされたのが島根大学から参加してくれていた学生2名のアイデアであり、それらについて「グローバルの見地から見てスケールアップが可能かどうか」「AIの社会実装といった観点で半導体マーケットの指数関数的な発展に絡めることが出来るか」「そもそもマーケットが存在するのか、マネタイズは可能なのか」という3つの視点より講評させて頂いた。
アントレプレナーシップ教育には弊研究所としてもこの数年、より一層力を入れて参画してきている。弊研究所のドメインは何といっても”情報リテラシー(information literacy)”の研究開発・教育普及である。しかし、先般明らかにした論文においても記したとおり、その先にあるものは何かというと、結局のところ「社会課題を見つけ、それを解決するという営みを持続可能な形で立ち上げ、続けて行くこと」と言う意味でのアントレプレナーシップの涵養に他ならないのである。したがって弊研究所としても、徐々に軸足をより広い観点からのアントレプレナーシップ、さらにはその教育へと移しつつあり、様々な大学や自主的な取り組みにおいてこれを展開してきているというわけなのだ。
そうした中で、今年(2025年)はとりわけArt/Technology/Entrepreneurshipのtrilogyでやっていければと考えている。technology、すなわち技術については弊研究所自身が既に人工知能(AI)の開発とその社会実装を生業とする「AIカンパニー」であることから明らかなとおりだ。これをとりわけ意欲ある学生インターン諸君と共にチームを結成して推し進めて来ており、今年(2025年)はその成果を国際学会で発表することまで企図し、着手しているところである。他方で、entrepreneurshipはというと、上述のとおり、既に様々な大学、具体的には広島大学教育学部、さらには東京大学大学院工学系研究科等において実施させて頂いてきており、自主的な枠組みも含め、さらにこれを拡充しようと考えている次第である。
これらに対してartと言われて、「はて?」と読者の皆さんは思われたかもしれない。しかしこれこそが、今後の我が国におけるentrepreneurship教育の目玉になるべきものであると私自身は信じてやまないのである。なぜか?
今年(2025年)はこれまたご縁あって、まずは初夏の段階で都内有数の美術大学において私自身、この意味での特別講義を複数回実施することで内定頂いている。そもそもこのお話を何故受けたのかというと、こうした思いがあってからなのである。我が国においては、とりわけ戦後の我が国では確かにものづくりの伝統により一層磨きがかかり、それが我が国の高度経済成長を実現するにあたったことは言を俟たない。だがそこでは常に「日米同盟」という下駄を履かせてもらっていたのである。すなわち「我が国は米国と同盟国。その我が国が富んでいることが自由主義・民主主義の最大の砦になるのだから、最大限稼がせててくれ」と米国勢に対して、あるいはそれ以外の西側の諸国勢に対しても暗に主張できたのである。だから「メイド・イン・ジャパン」は世界中のどこでも売りさばくことが出来、我が国は戦後、繁栄の一途を辿ることが出来たのである。
だがしかし、時代は変わった。―――もはやこうした仕組み、そして論理が通用しないことは、毎日の様にメディアを騒がせる「トランプ節」からも明らかなのである。そしてそこで必要なのは我が国自身が、自らの表現手段を用いて五感の全てを通じアピールすることなのであり、その際、中核となるのが言語表現もさることながら、それ以外の感性をフル活用したartに他ならないのである。
この点、しばしばグローバル社会ではデザイン思考(design thinking)が多く語られ、そこではart的な発想からあたかも摩訶不思議なプロセスを経て、ものづくりにまで至るかの様に描写される。しかしこれは一部の例外を除けばほぼあり得ないプロセスなのであって、technologyとentrepreneurshipのチームに表現部隊としてのartのメンバーが同時並行かつ自然な形で加わることにより、これまた自然な形でinsprirationが醸成され、それが類稀な表現を生み、人々に伝播していくというのが望ましいプロセスなのではないかと考えている。
「それではこれら3つの要素、それぞれに携わるチームメンバーたちにおいて共通の認識となるべきことは一体何であるのか」
そう、読者の皆様は恐らくお考えになるのではないかと思っている。ここで是非思い出してもらいたいのが、かつてドイツの美学者Baumgartenが美学を真反対の方向に据えてしまう「前」における「美」の在り方なのである。例えばミケランジェロの巨大な宗教画を想い出して頂きたい。あの様な巨大な作品を1人で創り出すことはおよそ不可能なのである。それではどうやったのかといえば、「美」そのものは神の恩寵として「既にそこに等しくあるもの」とされていたわけであり、その部分、部分を「親方(ここではミケランジェロ)」の下、携わる職人たちそれぞれが創り出していたのが実態なのである。すなわち、そこにあるべきなのは「共通認識」なのであり、それがさらには「個々人を超えた存在としての偉大なる何か」であったという点にこそ、今立ち返るべきだと私は想うのである。
この意味でart/technolog/entrepreneurshipのtrilogyから成る全く新しいフレームワークは、「新しく」もあるが、同時に「古来のもの」でもあるのである。自然(じねん)を捻じ曲げることによって人類にとって都合の良い何かを生み出すのではなく、「個々人を超えた存在としての偉大なる何か」に対する畏敬の念を忘れない中において、それでも何とかしてその一端でもつかみとり、この手で表現をし、もって社会課題を解決していく。これこそが、今後人類が総出で為すべきことなのではないか、と私は今、信じてやまないのである。
そして弊研究所は引き続きこの意味でのアントレプレナーシップ教育(広義での)を更に全国において、さらにはグローバル社会全体において推し進めていく。あるべき世界は一体なのであるか、その実現のために私たち日本勢は今こそ何をしなければならないのか、そしてその向こう側にある未来とは一体どういったものであるべきなのか。―――取り組むべき課題はまだまだ山の様にある。その一つ一つの山を乗り越えて行く旅に、共に手と手を携えながら今こそ、繰り出そうではないか。
2025年2月16日 岡山にて
株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 ファウンダー/代表取締役CEO/グローバルAIストラテジスト
原田 武夫記す
・・・
いかがでしたでしょうか?この話の「続き」にご関心を持たれた方は是非、来る4月に弊研究所が開催致します公開セミナーにお申込み下さい。詳しくはこちら(クリックするとご案内ページにジャンプします)からどうぞ!