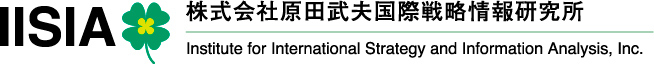「sakana.ai炎上事件」で考えたこと(「IISIA技術ブログ」Vol. 22)
純粋なる「技術ブログ」ではないことを御許し頂くとして、アクチュアルなテーマについて記したいと思う。我が国発AIヴェンチャーであり、かつ「ユニコーン企業」として期待の大きかったsakana.aiが今、”炎上”している件についてである。スタートアップ界隈でこの週末、大いに騒ぎとなっている件なので、読者の皆様もあるいはご存知かと想っている案件だ。
非常に簡単に言うと、同社が最近発表した論文で「性能が従来型よりも150倍も向上した」としていたものが、その実、「むしろ性能は劣化していた」ことが明らかになったというスキャンダルである。sakana.aiといえば、外務省時代における後輩のI氏が共同創業経営者に名を連ねる中、今年になってからも派手なメディア・キャンペーンが繰り広げられている有名スタートアップだ。ところがふたを開けてみると、極めて単純な「虚偽論文」を堂々公表していたというのであるからたまったものではない。幸か不幸か、我が国は本件がシリコンヴァレー発で勃発するや否や、連休に入ったのでメジャー・メディアではそれほど騒ぎには未だなっていないかの様に見える。しかし、実際のところ、同社から出資を持ちかけられ、実際にそれを受諾したかどうかにかかわらず、我が国大手企業のCVC関係者の間で噂は瞬く間に広まっているようだ。「出資を持ちかけられたが断った。あの時断ってよかった」(某大手企業CVC担当幹部談)といった声すら聞かれるほどである。また、本稿執筆段階(2025年2月23日夕方)で同社の技術ブログには本件についての釈明は掲載されていない。それに対して、我が国で活躍するエンジニアたちからも詳細な検証記事の掲載が相次いでおり(こちらが大変参考になる)、少なくともネット空間上では「勝負あった」といったところであろうか。こうした状況を踏まえ、この連休明けからさすがに我が国大手企業CVCの「サラリーマンファンドマネジャー」たちも自らの保身のため、同社に対する釈明を求める声が矢継ぎ早に上がり始めるのではないかと見ている(いや、ここまでの案件でありながら、そうした対応もせずに、wishful thinkingでやり過ごそうというのであれば大問題なわけであるが)。いや、それ以上に実はこのsakana.aiには我々日本人の「税金」が間接的に投入されていることを踏まえれば、ここは一つ、徹底的な真相解明が望まれるというべきなのではないかとも考えている。
本件を「調子に乗ったAIヴェンチャーによくありがちな不祥事」と片付けてしまうのは簡単だ。しかしより俯瞰しながら考えを進めるといくつかの基本的な学びがここからは得られるのではないかと想ので綴っておく。
第一に「AIヴェンチャーにそんなにカネがかかるのか?」という根本的な疑念である。「シリコンヴァレーにも根っこがあるチーム」「共同創業経営者らは日米でそれぞれ活躍した人物」「sakana.aiといった名前から感じられる親近感」・・・これらに惑わされて巨額の投資が為されたということは本当に無いのであろうか?筆者自身がAIビジネスを弊研究所で行い、かつアカデミアでもAI研究論文を発表する立場にあるのではっきりとわかるのであるが、AIビジネスに同社が調達したと言われる1600億円?もの資金が必要だとは到底思えないのである。そもそもなぜそんなに資金が必要なのか、今回露呈した同社の劣った企業統治構造を踏まえつつ、まずは再度、説明を求めるべきであろう。筆者自身がコーディングも行うので分かるのであるが、正直、この世界は大勢のプログラマーがいれば良いという世界ではないのである。あるいは同社は巨大で壮麗なオフィスが無ければ売れない代物を売っていたのか?正直、依然としてlaboratoryの域を越えないことしか対外発表をしていない同社であるだけに、「少ない原資で大きな利益を生む」というのがビジネスの基本であることを踏まえると、甚だ疑問無しとはしないのである。
第二に「我が国においてはとりわけ責任を問われるであろう日本人共同創業経営者のI氏に、技術を見る眼はあったのか?」という点である。略歴を拝見する限り(これは外務省キャリア官僚の略歴を見れば他も同じであるわけだが)「人工知能科学」で修士以上の教育を受けた形跡が同人には全く見受けられないのである。「いや、チームで最後はやるのだから、共同創業経営者の別の人物がAIの世界では知らぬ者がいないほどのレヴェルである以上、全く問題ないのではないか」と読者は考えるかもしれない。しかし、それこそ、スタートアップの経営を本当にしたことない者の戯言なのである。無論、平時であれば良い。しかし今回生じた様な「有事」、しかも部下がしでかしたことに対する火消といったリスクマネジメント案件になった時にこそ、「経営者が最後は自分自身で技術開発、製品製造についてもその手でグリップ出来るか否か」が問われるのである。「いや、これは技術案件であり、経営案件ではありませんので、今しばらくお待ちください」などとまさかI氏は言わないであろうが、しかし日本時間で図っただけでもこの虚偽論文が掲載れ、批判を受けてから既に3日も経過しているのである。「最高経営責任者(CEO)」として何らの釈明も出来ないということ自体が、とりわけ「ものづくり」の伝統のある我が国経済界ではおよそ受け入れられないということを、今後、同社、そしてI氏は思い知ることになるのではないだろうか。老婆心ながら、大変気になるところである。
第三に「AIビジネスの最前線は処理速度なのか?」と言う点である。私自身、大規模言語モデル(LLM)とその社会実装を中心とした研究にあたっているのでよく認識しているのであるが、AI研究の最前線はもはやスピードではなくなりつつある、というのが正直なところなのである。ましてや同社の様に巨額の資金を必要とする処理速度の高速化が最前線ではなく、むしろその点についてはグローバル社会全体で伸び悩む中、やはり各ドメイン(分野)別に社会実装をどの様にきめ細かくやり、コスパ、タイパを上げつつもビジネス的に意味のある付加価値を生み出せるのかが勝負になっているというのが現状なのである。事実、我が国のAIヴェンチャー各社は事実上、その意味でのコンサルビジネスに入り、これはこれで「沼って」しまっているのが現実なわけであるが、そうした中で従来型の開発を標榜してきたのが同社なのである。「セコハンのGPU」をシンガポールから調達し、一夜にしてOpenAIからお株を奪ってしまったDeepSeekを見れば、今何が起きているのかはこれまた明らかであろう。仔細な背景事情は分からないが、今回、明らかに最高技術責任者らのチェックを万全に受けていない形で対外公表が「虚偽論文」についてなされてしまった背景には、こうした中での同社の「焦り」が自ずから表出してしまったということがあるのではないだろうか。
いずれにせよ、今回のsakana.ai炎上事件はAI開発、AIビジネス、そしてAIスタートアップ投資、さらにはアントレプレナーシップ論全般と言う観点で極めて学びの多い事案であったと考えている。経営の最高責任者であるI氏が一刻でも早く、本件について全うな火消しを図ることを強く期待している。何はともあれ、我が国外務省から飛び出し、スタートアップ界隈でのろしを上げたという意味では私とは「同志」なのであるから(ちなみに同氏が外務省国連行政課に勤務していた時代に、私はとある「やんごとなき案件」の関連で大変お世話になったことがある(が恐らく、同氏は記憶すらしていないであろう))。時間が経てば経つほど、リカヴァリーショットは難しくなる。そういった事案が「全世界的な株価暴落」が生じている今、炸裂してしまったことからも、I氏の上記の意味での奮闘を期待するところである。さもなければ・・・本当は岩盤である我が国経済の「中枢」に残念ながら同社は入っていけないのではないか。そう危惧している。
2025年2月23日 東京の寓居にて
株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 ファウンダー/代表取締役CEO/グローバルAIストラテジスト
原田 武夫記す