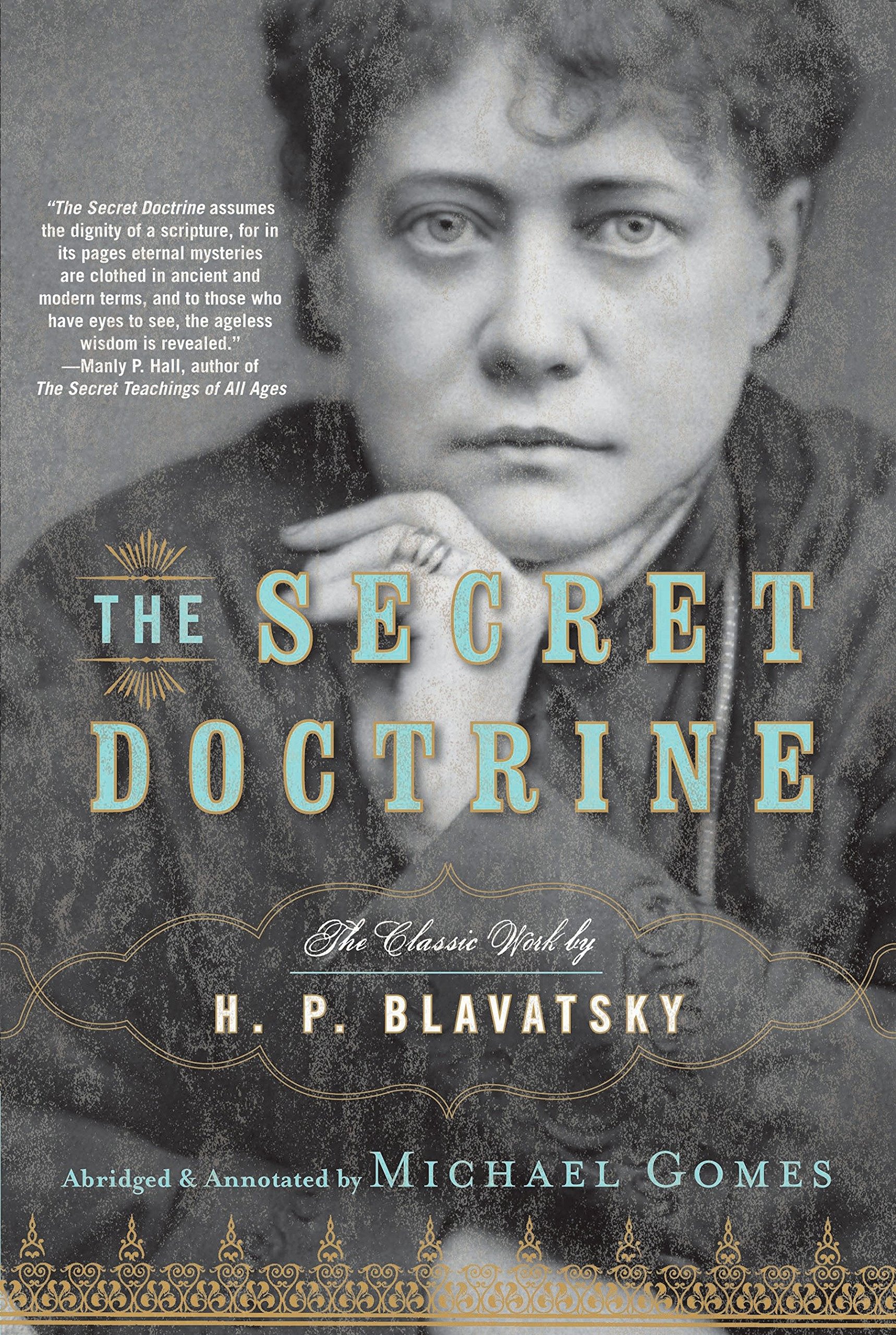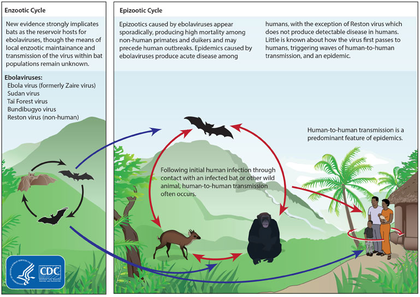「魔都・上海にて想うこと。」 (連載「パックス・ジャポニカへの道」)

今、このコラムは朝食ミーティングのために訪れた中国・上海の名門ホテル「花園飯店」の一室で書いている。天気はうす曇り、と言うより、ここのところの御多分に漏れず、軽いスモッグ気味のガスが朝から垂れこめている。
昨日は16時頃まで自宅の書斎で執筆をしていた。それから夕方の便に羽田空港で乗り込み、一路、上海へ。22時半過ぎにはこの「花園飯店」に着いていた。今回の用務は新しい華僑の若きリーダーとの定例ミーティングを行うためなのだが、「このタイミングでしか会うことが出来ない」と指定され、朝食がてら、ということになったものだ。無論、意味があるミーティングになることがあらかじめ分かっているからこそ来ているわけだが、それにしても便利になったものだ。隣国とはいえ、上海はもはや再び私たち日本勢にとってここまで日常的な現実(リアリティー)になっているというわけなのだから。
最初にこの地を訪れたのは1999年3月のことだった。北京と組み合わせで旅行にて訪れたのだが、あの時起きたいくつかの出来事は忘れれらない。まず、いずれの土地でも空は真っ青な青空だった。今のようにスモッグが垂れ込めるということは無かったのである。それがまず第一点。
次にまず北京においてだが、天安門広場前の大通りを埋め尽くしていたのは今のように自動車であったり、あるいは電気スクーターではなく、正真正銘の「自転車」であった。しかもそれを漕ぐ人々は全員が人民服を着ていたのである。これまた今では信じられない光景だ。
その後、北京から上海へと空路で向かったのだが、それがまた大変だった。出された昼食がなにやら怪しいなと思ったのだが、とにかくそれに明らかに「当たった」のである。途中、珍妙な味がし、「これは化学薬品なのではないか」と直感的に思ったが、同行者の手前、そのまま食べていたのである。だがその後、上海に着くやいなや、何とも形容しがたい不快感・吐き気に襲われたのである。「このまま死んでしまうのでは」と本気で覚悟したが、4、5時間ほどこの「花園飯店」のベッドに横たわり、安静にしていたらば治った。
しかし、災難というものは続くものである。その日の夜は上海を貫く大河でクルーズを、としゃれこんでいたのだが、そこで出された食事にまた「当たった」のである。パクチーを口に含んだ瞬間に「これは何か変だぞ」と思ったのだが、とにかく食べ進んでいると、また同じ何とも言えない吐き気に襲われたのである。だが、船上であり逃げ場がない。食事を止め、デッキで夜風に吹かれて、何とか気を紛らわして、早々に下船した。
「一体あれは何だったのか」
そう今でも想い出すのだが、要するにその後、我が国を巻き込んで大騒ぎになるこの国特有の「食の安全」の問題が既に現れていたということなのだろう。それにしても、あの時は(今では笑いごとだが)「客死」という文字すら、頭の中で踊ったほどの苦しみだった。
上海は「魔都」としてのかつての面影をところどころ残してはいたものの、一歩街角に入り込むといわゆる「スラム」に近い街並みだったことをよく覚えている。地下鉄はほとんど整備されておらず、乗り合いバスに乗ったり、あるいは台数の少ないタクシーに乗り合わせることをよしとしない私たちは徒歩で市内を廻った。「万博」を契機に東京以上の地下鉄網を持つことになるこの街・上海なのであるが、まだ不完全な地図を片手に右へ左へと歩き、観光スポットを廻ったものである。
その当時、「伊勢丹」が市内にはあり、周囲とは明らかに違うこぎれいな商業ビルの中に在った。品揃えは決して多数とはいえなかったが、とにかく「日系デパート」「日本語」に出会えたことで言いようのない安堵を覚えたことを今でも良く覚えている。
今滞在している「花園飯店」はそのころから屹立していた。そして今と変わらぬ「ホテル・オークラ」系であり、同じく日系で「ホテル・ニューオータニ」系の北京になる名門「長富宮」と並んで、当時の邦人観光客にとっては定番の宿だった。しかし今と全く違うのは、とにもかくにも周囲に高層ビルなど全く存在せず、旧ソ連など共産圏にありがちな「外貨(ハード・カレンシー)を外国人に落とさせるためのホテル」そのものだったということだ。ホテルの中はそれなりのレヴェルだが、一歩でも外に踏み出した瞬間、そこは全くの別世界となる。私たち日本勢の目から見るとどうひいき目に見ても「スラム」としか言いようのない場所では、男性といえば擦り切れた短パンに薄汚れたタンクトップの下着を皆着ていた。所在なさげに街角に皆でたむろっては中国将棋を差している。女性たちは何やら忙しそうに家事をやっているが、これまたみすぼらしい恰好を皆が皆している上に、年齢を問わず化粧気が全くない。そしてその脇を子供たちが奇声を上げながら駆け抜けている―――。
あれから17年。この街、そしてこの国は明らかに変わった。遅くに浦東空港に到着し、車で高速道路に乗りながらホテルへと向かうと、旅行に慣れていない人ならば「ここは日本です」と言われても分からないのではないかと思うような夜景なのである。そして朝を迎えてこのコラムを書いている私の目の前で、窓外には高層ビルが群生している。そう、文字どおり「群生」しているのだ。その数は東京の比ではないのである。
先般、ヴァチカン勢はこの街・上海で選任される司教ポストを巡って中国勢と合意に達した。そしてそのヴァチカン勢がグローバル・マクロ(国際的な資金循環)の総元締の一つであることを踏まえれば、これからこの街へと大量のマネーが流し込まれることは既に明らかなのだ。中国勢の全土はともかくとして、この「魔都」はさらに劇的に変わり続けることであろう。そしてそのことは空港に到着した瞬間に出迎えてくれる「蛇腹」の壁面が全て「HSBC」の広告によって埋め尽くされていることから強く予感した。香港「上海」銀行、サッスーン家の再来である。
もっとも先般、五大客家の一つの「太人」(頭目)が私にこんなことを教えてくれたのである:
「漢人たちは久々に中国全土に対して権力が行使出来てうれしくて仕方がないはず。しかしだからこそそれを維持するために、国家主席が変わる度に全土で利権集団が入れ替わるようにしている。日本人は“爆買い”といって喜んでいるが、それもつかの間であり、政治リーダーが変われば、その“爆買い”の担い手も次々に替わる。つまり中国ではその繰り替えしである以上、安定的に中間階層が育つとういことはあり得ないわけだ。それなのに日本企業はといえば、存在すらしない”中間階層“を念頭においた商品ばかりを中国本土へ売り込もうとして大失敗している。何時になったらばそのことに気付くのか」
今から更に17年後というと、丁度私自身が還暦を越えたあたりである。かつて「魔都」と言われ、その後、我が国の旧軍による「事変」で破壊された上海。戦後も貿易の拠点として栄えるものの、やがて1960年代後半から突如として始まる「文化大革命」ではその震源地となり、再び荒廃した。そしてそれが過ぎて始まる改革開放路線の中で再び経済拠点として発展している。そんなこの街・上海はその時、一体どうなってしまっているのか。
金融マーケットでは今、「香港」の機能は「海南島」に移されることになると語って止まない向きもいるくらいだ。それがすぐさま上海と競合することにはならないであろうが、住環境とそこに暮らす人々の人柄という意味では全くもってより好ましい「海南島」との比較で果たして上海はどの様なポジショニングを維持していくことになるのか。
己の17年前から現在に至る道のりを思い起こしつつ、かつ今現在から今後17年の間に何が起きるのかに胸を躍らせながら、魔都・上海は今日もまた新しい一日を迎え始めている。
2016年3月27日 中国・上海にて
原田 武夫記す