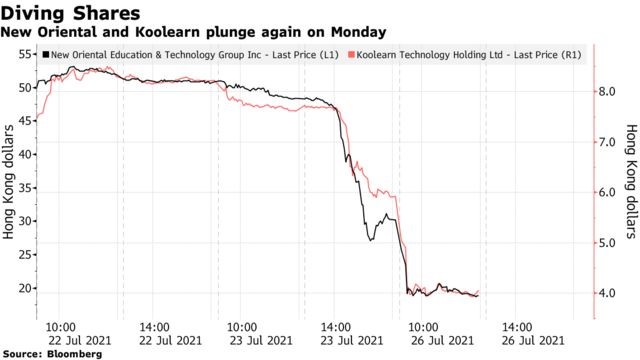舞踊という生(連載「美と心の旅」・その6)

特別コラムニストのふらぬーるです。今までのコラムでは絵画や仏像をとりあげてきましたが、今回は身体表現による芸術についてお話ししたいと思います。
一般人がその顔、身体を不特定多数にさらけ出すという行為は、Facebook, instagram, youtuebeという媒体の登場によって一気に加速しました。
本屋に行けば、まず目に入ってくるのはモデルや芸能人が巻頭を飾る雑誌、週刊誌類ですが、
記事には無名の記者でさえ写真を添え、広告項にはすべて顔があります。
顔や身体の形象そのものによって生計を立てていない人でさえ、自分のそれを意識せざるを得ないのが現代と言えるでしょう。
ミラン・クンデラの小説『不滅』の第一部『顔』に、こんな一節があります。
「あたしたちは自分の名前をまるで理解していないし、名前の歴史についてなにも知らないのに、それでも高ぶったような忠実さでその名前をもちあるいたり、それと一体になったり、とても好んだり、まるで天才的な霊感の働きのもとであたしたち自身が発明したかのように、滑稽なほど鼻にかけたりしているわ。
顔にしても、同じことよ。覚えているけど、あれは少女時代の終わりころのことだったはずね。鏡で自分のことをとっくり観察しすぎて、あたしはとうとう、自分の見ているものがあたしなのだと思うようになってしまった。(中略)
鏡の前にいると、これが本当のあたしかしら?なぜあたしはこれと連帯しなければならないの?と考える瞬間がやってくるの。」
「鏡のない世界で生きてきたらと想像なさってみてよ。あなた自身のなかにあるものそのままの、一種の外的な反映をきっと想像したでしょうね。」
随分と昔、私も同じことを考えていました。
生涯直接見ることのできないこの顔、この身体を持つのは紛れもない私自身であるという事実に日々向き合わねばならない私たちは、我々の身体をどう見せるか、どう表現するかに注意を注がざるをえません。どのような表情をして、どのような化粧をして、どのような服を着るのかということに。
それらは日常における外的世界への表現であり、意識せずとも誰しもがどう自分の身体と共に生きるか日々考えているといえるのではないでしょうか。
自分の身体に耳を澄まし、身体自体を解き放つこと。
ある人は、自分の身体をまじまじと見ながら心安らぐまで温泉で脱力することだと言うかもしれません(笑)
しかし、指先まで自分の身体に全身全霊で耳を澄ますということはとても難しいことであり訓練と技能が必要です。それを極限まで追求しているのが舞踊家であり、身体を熟知し、解き放つ彼らの実践はまさに芸術である、と私は思っています。
コンテンポラリー・ダンスをご覧になったことはありますか。
コンテンポラリー・ダンスの基礎になったのは意外かもしれませんが、日本の暗黒舞踏派という前衛的な舞踊です。「イマジネーションと身体を結びつける回路の開発」「立ちあがるどころか、体を動かせるようにする所からはじめなくてはいけないダンス」という思想が根底にあります。*
先日、コンテンポラリー・ダンスの大家のピナ・バウシュを取り上げた映画『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』を鑑賞しました。彼女は、フェデリコ・フェリーニの映画『そして船は行く』や坂本龍一のオペラなどにも出演しており、ゲーテ賞も受賞している振付家ですが、2009年に亡くなっています。
『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』 予告編
彼女が監督した作品を見ると、人間の身体それ自体がこれほどまでに芸術をつくりあげられるのか!と感嘆せずにはいられません。
ピナ・バウシュの踊り続けるいのちから、わたしはニーチェの舞踊哲学の要素を感じます。
「生とともにいるとき、舞踊に熱狂して揺れ動かずにはいられなくなる。」と説くニーチェは、彼の著作『ツアラトゥストラはこう言った』の中で、生は日常的レベルにおける苦痛に満ちた生と、そうした日常性とは一線を画する、形而上学的慰籍をもたらすという生という、生の二元論を展開しています。
身体のみの表現である舞踊は、言語活動に支えられている我々の自己意識そのものへの深い問いかけを発します。言語化できない身体表現の可能性を提示する舞踏を通じて、鑑賞者は人間の身体の神秘性に息を呑みます。
そして自分の身体についてほとんど知らず、思うように動かせない私は、それを大変もどかしく思い、身体ひとつで生の芸術を体現する踊り子たちに憧れてしまいます。
参考URL
*http://www.albatro.jp/birdyard/movie-live-action/butoh/index.htm