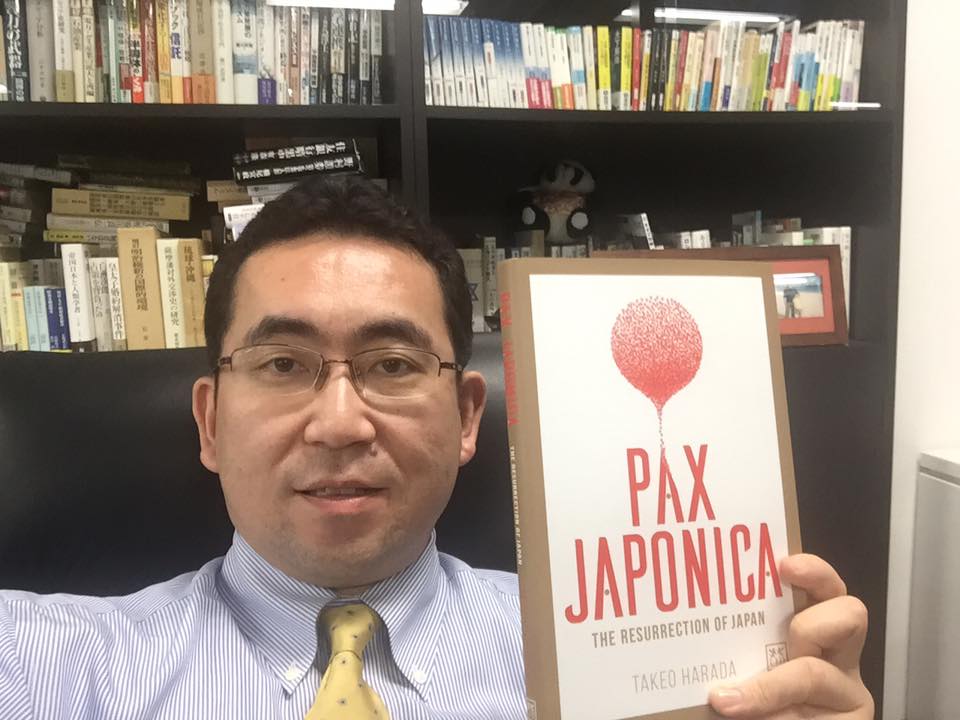複合分野リーダーシップの時代が始まる (連載「パックス・ジャポニカの時代」)

「人はパンのみに生きるにあらず」有名な警句である。いやしくも人間として生まれたのであれば、糊口を拭うためだけに仕事をするのではなく、人間たるもの、いかにして生きるべきかを常に考え続けなさいという趣旨だ。
だが、そうは言っても現実は全く甘くない。外務省を自主退職し、“娑婆”に自らの意思で飛び込んでから10年が経った。そして未知の世界であった「経営」をこの手で行うようになってから8年の月日が経ったわけだが、その中で日々感じるのは「世の中は激烈な生存競争の場である」ということだ。
事実の問題として経営者目線で言うことをお赦し頂けるならばこういうことだ。―――一見すると全く同じように見える私たち日本人。しかしその間では明確に意識の違いがあり、そのメルクマールとなっているのが「年収」である。額面の年収が400万円、600万円、1000万円、そしてその次が1800~2000万円以上、といった具合に4段階で明らかに今現在の私たち日本人は分けられている。ちなみにこれは「額面の年収」であり、実際に手元に残る「所得」というベースでいうと話は全く違ってくる。
もっというと額面の年収が2000万円以上になってくると、次はフローではなくストック、すなわち「資産規模」の世界に入って来る。ここから先の世界についても念のためにいっておくと、金融資産が1億円以上というのが次のハードルであり、更に「現預金」で200億円以上というのがさらにその次ということになってくる。もちろん、上には上がいる。
私が言いたいのは要するに現実問題として「金銭」で測る限り、明らかに差が隣の人との間ではありますよということなのだ。そして日々、私たちは意識・無意識にそのことを考え、少しでも上に行こうと努力しているのだ。「草食系」と世間では言われる若い世代も、さすがに額面の年収が200万円を切る世界には入りたくないはずだ。つまり、私たちは総じて「パンのみに生きている」ということになりかねないというわけなのである。
しかし、である。たとえばここで手元に「5000億円」が何等かの理由で転がり込んでくるとしよう。しかも現預金という形で、である。「まさか」と思われるかもしれないが、私が知る限り実のところそうした人々は数多く我が国にもいる。ある日突然、「そのようなもの」として選ばれ、その預金口座に明らかに桁の違う金額が振り込まれて来るのである。
その様な人物の一人を知る方から、こう言われたことがある。
「原田さん、考えてもみてください。毎晩、銀座や赤坂で100万円以上使ったとしても到底使い切れないくらいの金額の“利子”がそれだけのお金を預金していると入って来るのです。『もう使い切ることが出来ないよ』と嬉しい悲鳴を聞いています」
「パンのみに生きるのではない人生」―――これをイメージする時、私たちは必ずや3つのタイプに分かれるのではないだろうか。1つは不意に「生きることそのもの」に対する前向きな意識を失ってしまうタイプだ。何せ「パンを得ること」がそれまで目的だったのに、肝心の「パン」はこれから山のように、そう、それこそ無尽蔵に湧いて出て来るからだ。「なぜ自分は生きているのか」という”生存の危機“にすら精神的に追い詰められる危険性がある。
第2に、そもそもカネではなく、自己の創造行為こそ「生」の本質だと達観しているタイプである。作家や芸術家がこのタイプに当てはまる。最初からカネには無頓着であるので、1億円であろうと、5000億円であろうとどうでも良いのである。ただひたすら創りつづける、そういう人生を孤独に送り続けることになる。
そしてもう一つのタイプ。大変長くなったが、これがここで取り上げたいタイプなのである。「パンを得ることだけではない人生」という最初の極みに到達した時、人間たるもの一体何を考えるのであろうか。カネは目の前において、それこそ泉から清水が湧き出て来るように次々に飛び出してくるのである。最初はその姿に圧倒されるやもしれない。だが、そのユーフォリアを超えた瞬間に私たちははたと立ち止まるのである。「何のための人生なのか」と。
そんな一連の事共を考え始めた矢先、カナダにいる友人Matthew Thomasから「これ、読んでみてくれ」と1本の英語論文が送られてきた。タイトルには”Building a Life: The Gifts of Breadth in a World Sold on Depth”とある。何でも今年(2015年)の秋にOxford University Pressから出される論文集に寄稿している文章なのだという。
Matthew Thomasとはひょんなことから知り合った。カナダ出身で“Young Diplomats of Canada”といったプロジェクト、さらにはG20を支える一つの会合であるY20でも活躍した彼は、ハーヴァード・ビジネス・スクールで全く新しいリーダーシップ論に取り組むことになる。政官・ビジネス・NPOの3つの分野を跨ぐ、英語でいうとtri-sector leadershipというコンセプトに基づくリーダーシップ論だ。このコンセプトについて我が国では未だ熟した訳語がないので、ここでは「複合分野リーダーシップ」とでもしておきたいと思う。
Harvard Business ReviewにMatthew Thomasが寄稿した論文を見て、私は「これだ!」と直感した。なぜならばそこに書かれていた方向性は、他でもない、かつて外務官僚であり、現在は経営者であり、同時に社会活動家・言論人でもある私が目指していたものそのものだったからだ。そして早速、公式英語ブログで私なりの考えを発信したわけだが、最近は実に便利なものだ、「検索(retrieval)」で直ちにMatthew Thomas自身がそれを見つけ、私に直接コンタクトしてきた。どうやら「日本では複合分野リーダーシップに類するものがあるのか」という点に大いなる興味を持っているようなのだ。そしてその後、非常に緩い形でやりとりを続けてきている。
上述の論文は、これまでの彼の研究を分かりやすく、かつその論点を網羅的にまとめたものだとの印象を受けた。その要点を述べるとこうなる:
―これまで近現代社会は「専門家による支配」の時代であった。社会はあらゆる分野において細分化してきたため、それぞれの分野での専門家が実力を持ってきたというわけなのである。だが2008~2009年に(最初の)クライマックスを迎えた金融メルトダウンで様相は一変した。なぜならば他ならぬ「金融の専門家たち」が絶対に大丈夫だとして構築・運用してきたシステムそのものが崩壊したからだ。
―そのため、「より広い分野を跨ぐリーダーたち(broad leaders)」が今、必要とされている。そのスペックは次の4つである:
・芸術、化学、エンジニアリング、ビジネスそして法律といった複数の分野を理解していること(intellectual breadth)
・地理と文化の違いがどれほどのインパクトを目の前にある問題に対して与えているのかを理解していること(cultural breadth)
・ファイナンス、人財、そしてオペレーションといった異なる機能がどのような形で互いに情報共有し、協働することになるのかを知っていること(functional breadth)
・「食糧、水並びにエネルギーから成る複合体」といった様に異なる産業分野同士の相互作用をポジティヴに評価していること(industry breadth)
―こうした幅広く、かつ分野を跨ぐリーダーシップが求められているわけであるが、その性格付けを更に詳しく述べると次のとおりとなる:
・「全てを知っているが、何についてもマスターしていない(jack-of-all-trades, master of none)」であってはならない。そうではなくて、「全てを知っていて、しかも一つについて習熟している」というタイプである必要がある。そのためには自分自身が一体どの分野でインパクトを優先的に与えることが出来るのかをまずもって探し出す必要がある
・異なる文脈を超えて適用することのできるスキルを持っていること。そしてそうしたスキルを意識的に学び、修得していく必要がある
・自分自身のキャリアや知識を乗り越えるべく、様々な人的ネットワークの構築に励むこと。それによってトップ・レヴェルのリーダーシップを示すためのチームを作り、インパクトをもった意思決定を行うことが可能になってくる
・相互に異なるセクターにおける文脈において横たわっている事柄同士でどこが似通っているのか、またどこが異なっているのかについて根本的なレヴェルより理解出来ること。これを「文脈に対するインテリジェンス(contextual intelligence)」という
・自らが抱く様々な動機の間でバランスを取っていくことが出来ること。「豊かになりたい」「良いことを行いたい」「変革をもたらしたい」「権力を持ちたい」あるいは「自分自身を改善したい」といった様々な動機を、複数のセクターを乗り越え、かつ己は公共のための価値を創造しているのだと確認することによって調整することが出来なければならない
それではこのような「複合分野リーダーシップ」は一体どのようにして生じるのであろうか。Matthew Thomasらはこのことについて世界各国の当該リーダーたちに尋ねたところ、多くの場合、こんな回答を得たのだという。
「単にそうなっただけなのです(It just happened.)」
そしてある者はこうも語ったのだという。
“In the fields of observation, chance favors only the prepared mind.”
心の準備をしているものだけが、省察の中でチャンスを見出すことが出来る、というわけだ。
Matthew Thomasらはこうした形で現実に存在している「複合分野リーダーシップ」は単に個人として今後も生成されるべきではなく、ある種の「エコシステム」を社会において形成させるべく、組織・企業が積極的にこれに取り組むべきだと述べている。ちなみにこの論文集の編集責任を負っているのはglobal consulting firmの雄の一つであるMcKinsey & Companyである。かつて1997年の段階で「人財獲得戦争(War for Talent)」を同社が論文をもって掲げた後、実際、米国勢、そして欧州勢は少しでも付加価値を生むことが出来る人財の獲得を世界中で行った。2009年に生じた「円高」でかろうじて事の深刻さに気付き、「グローバル人財育成」などと大騒ぎを始めた私たち日本勢は完全に出遅れてしまったことは記憶に新しい。今回のこの「複合分野リーダーシップ」についても全く同じ展開になるのが目に見えている、と私は直観的に考えている。
もっとも大変難しいのは少なくとも現状を見る限り、我が国においてこの「複合分野リーダーシップ」が自然発生することはあり得ないというのが現実だということである。先般、英語公式ブログにおけるコラムでも書いたが、この点に関する卑見を簡単にまとめるとこうなる:
―我が国においてもっとも卓越した「問題解決能力」を持っているのは官僚たちである。だが、金融メルトダウン発生後の大いなる変調が続くグローバル経済の中で「自由貿易を掲げれば他国から容易に国富を獲得することが出来る」などということはもうなく、かつそもそも少子高齢化で納税者が減りつつある我が国において、官僚たちが「問題解決」の結果として創り上げてきた利権構造そのものが消滅しつつある。私たち日本人が「親方日の丸」であったのは官僚たちが利権構造を創り、国富を分配してくれたからであり、そうでない以上、官僚たちはバッシングの対象であり、サンドバックのように殴られ続けるべき存在ということになってくるのだ(特に「自由貿易による国富獲得」を果たせず、かつ国内利権を創出する役割を負っていない外務省)
―そうした中で政治及びマスメディアにおけるエリートたちも、変質してきた。かつては官僚たちと共に上記の意味での「利権構造」の構築を陰に日向に行って来た(そしてその利益を優先的に享受してきた)彼らであるが、「顧客」である一般大衆(有権者、視聴者)の満足度をあげるため、官僚バッシングをいかに派手に行うかだけに専心し始めたからだ。その結果、政治・マスメディアの双方においてポピュリズムが横行し、とりわけ官僚制との間で生じた亀裂はもはや修復が不可能なレヴェルにまで達している
―一方、ビジネス・リーダーたちはどうかというと、これもまた心もとない。大企業(big corporates)の「雇われ社長」たちはいずれも自ら価値を生むイノヴェーション人財ではなく、単に経費削減に励む管理型人財に過ぎないため、ヴォラティリティが激しくなる中であっても付加価値を生むという意味での「問題解決能力」をそもそも持っていない。それでは中小企業、あるいはアントレプレナーについてはどうかというと、「ホリエモン」に代表されるような「既存の権力構造に対するファイティング・ポーズ」をとる経営者がモデルとして定着してしまったため、ここでもまたポピュリズムが主流となっている。しかもそこで生み出されているものは金融資本主義の亜流による一時的かつ急激な富の集積に過ぎない(例「アフィリエイト」)に過ぎないため、拝金主義との誹りを免れないものである。「分野を跨いでリーダーシップを発揮し、世界を変えて行こう」などという気概を彼らが持つわけもないのである
―唯一望みを託せそうなのが市民社会(civil society)、すなわちNPOの世界なわけだが、これもまた課題が無いわけではない点に留意しておかなければならない。いわゆる「左翼」の巣窟であった「プロ市民」の世界を大きく変えたのが、2011年3月11日に発生した東日本大震災であった。復興支援を通じて広くネットワークが自主的に構築される中、全く新しいリーダーシップが登場し、ハイライトされたことは事実である。だが、哀しいかなこの「市民社会」はいってみれば“永続革命”のようなものであって、常に解決されるべき「イシュー」がなければ離散してしまうという根本的な問題を抱えているのだ。しかも「天変地異」の様な、規模は大きいがある意味非常に分かりやすい問題であれば良いものの、金融資本主義の次の時代の社会・政治・経済システムを創り上げるといった高い理解度を必要とするイシューには不向きだという構造的な欠点も抱えている。そのため、東日本大震災を契機として注目された我が国のリーダーたちは「その次」を巡って考えあぐねているように見受ける。そうこうしている間に「震災の記憶」は風化し、これらリーダーたちは元ある塒(ねぐら)の中に帰っていくことを余儀なくされている。有事を超えれば行政(官僚制)も彼らと手を組むことはまずなく、またポピュリズムが支配する政治やメディアは真っ先に彼らのことを忘れるからである
「日本に複合分野リーダーシップは存在し得るのか」―――そう問いかけて来る友人Matthew Thomasに対して私はこう答えておいた。
「そのための契機として、全ての人々を覚醒させるような重大事が日本では発生する必要があるのではないだろうか」
私はここでいう「重大事」こそ、我が国の本当の「権力の中心」が静かに、しかし着実に動かしてきている、我が国における事実上の「デフォルト(国家破綻)処理」であると考えている。“その瞬間”に、分野を跨いだ卓越したリーダーシップが、「もはやパンのみに生きているのではない」選ばれし真の富裕者と結託する形でこの国の枠組みそのものを変えていくことになるのだ。米欧の統治エリートたちは、実はそのことに気付いているのではないかとすら感じている。その意味で「複合分野リーダーシップ」の萌芽が我が国の一体どこでまず見出せることが出来るようになるのか、その“現場”から目が離せない。
2015年5月17日 東京・仙石山にて
原田 武夫記す