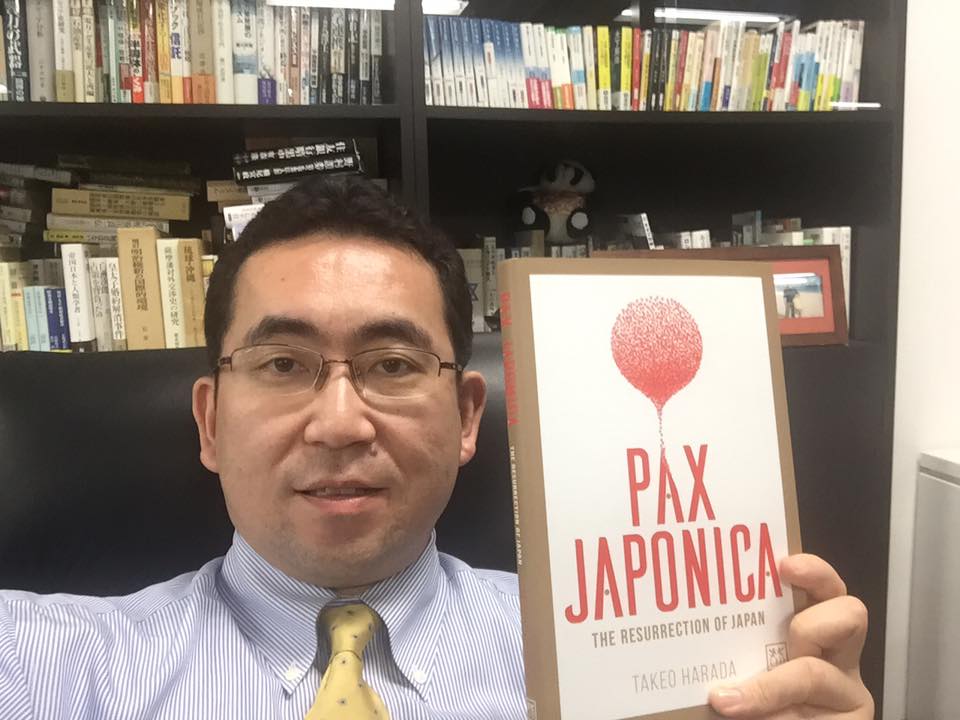安倍、石破、そして私。(続・連載「パックス・ジャポニカへの道」)

去る20日に我が国の自民党で「総裁選」が実施された。投開票の結果は読者の皆様がご存じのとおりだ。安倍晋三総理大臣が「三選」を果たし、石破茂・衆議院議員が敗北した。もっとも後者についても惨敗ではなく、「総裁選後に影響力を維持するための必勝ライン」として語られていた200票を裕に越える254票を獲得した。そのため「安倍一強」と何の留保無く言うにはやや厳しい状態であることが露呈したというのが正直なところだろうか。
だが、そんなことはどうでも良い、というのが私の心境だ。なぜならばこの(つくられた)「結果」を見て私の心中にはあらためてこんな言葉が思い浮かんでいたからだ:
「世の中に偶然など一つも存在しない。私は賭けてもいい」
かのフランクリン・D・ローズヴェルト米大統領が遺した言葉だ。そして私は安倍・石破のコンビを見る度にいつも思い出すことが一つあるのである。
2005年3月31日。一介の若手キャリア外務官僚に過ぎなかった私は自らの意思で外務省を後にした。それから2、3か月も経った頃のことだろうか。私が夕刻に東京駅前の八重洲ブックセンター前を歩いていた時、携帯電話の着信があったのだ。
見知らぬ番号であったが出てみると「テレビ朝日のディレクター」と名乗る人物であった。「何ですか?」と話を促すと「ウチの田原総一朗が是非、原田さんに番組に出て頂けないかと強く申していまして・・・」という。かつて日曜日午前の人気番組として知られた「サンデープロジェクト」への出演であった。
私は「田原総一朗」という人物がどうも好きになれない。類まれな知性の持ち主かもしれないが、他人の話の腰を必ず折り、それにかぶせて強引に自分の意見や質問を述べては、最終的にその人物をテレビ・カメラの前でねじ伏せてしまう。1980年代後半からどういうわけかテレビを席巻するようになった彼のこのやり方に大いなる違和感を感じ続けていたからだ。そのことは2005年春の自主退職直後であった当時もまた抱いていた強い想いだった。
そんなわけであったので私はにべもなく誘いを断ろうとした。しかし担当ディレクター氏もさることであり、半ば泣き落としまでかけてきたのだから致し方が無い。「分かりました、一度お伺いしましょう」と20分ほどすったもんだした挙句に折れた私の声を聴いて、心の底から安堵の声をあげてきたディレクター氏の様子を今でもはっきりと思い出す。
そして当日。六本木ヒルズにあるテレビ朝日のスタジオを訪れた私は正直面食らった。「ここが控室です」と案内された以外に何の打ち合わせも無いのである。お決まりの台本も無く、ある者といえばペットボトルのお茶の脇に置いてある「ロケ弁」だけだった。もっとも私は「そんなこともあるだろう」と思い、ペットボトルのお茶にだけ口をつけ、30分ほどの間、殺風景なその控室で時を過ごしたのである。
「原田さん、本番です。移動お願いします」
ディレクター氏がいよいよ登場したのは本番1分前だった。襟を正して楽屋を出ると斜め前の小部屋でしきりにドライヤーで整髪をしている音が聞こえてきた。特に関心は無かったがそこが通り道であったので脇を通ろうとすると件のディレクター氏が気を利かせ、この小部屋の主に声をかけてくれたのである。
「原田さんです。今日ご一緒させて頂きます」
「あぁ、あなた、どこかで会ったことあるよね」
声の主は・・・石破茂だった。見ると防衛省につくらせた「想定問答集」と書かれた分厚いファイル2冊を机の上に並べ、熱心に勉強していたようだった。メイクさんがそんな石破茂の整髪を手際よくしていた。
「いいえ、会ったことありませんよ」
そう言うのも何とも素っ気ないなと想い、私は軽く会釈をして通り過ぎたのであった。そしていよいよスタジオに向かう。スタジオの中からは田原総一朗が何やら大声で話しているのが聞こえてくる。そんな中を私は突き進み、ディレクター氏が「ここです」と教えてくれた座席に座ったのである。
するとそこには既に先客がいたのであった。カメラに向かって私から数えて二つ隣の席にその先客はいた。私は軽く会釈をした。「先客」もやや緊張気味ながら微笑みつつ頷き、「どうも」と小声で言った。
安倍晋三との3回目の出会いだった。1度目は九州・沖縄サミットの「森喜朗総理大臣主催官僚向け打ち上げ会」のテーブルでだった。その時、私の左隣に御仁はいた。注がれたビールに全く口をつけずにやや疲れているかの様な印象を与える人物だった。そして二度目は藪中三十二・外務省アジア大洋州局長と共に「北朝鮮問題」に関するブリーフィングをするため、自民党幹事長室に行った時のことである。かつ丼をランチとして頬張りながら、局長からの説明を「うん、うん」と静かに聞いていたのが印象的であった。そしてこの時、だったのである。
「本番1分前です。・・・30秒前・・・10秒前、9、8、7・・・」
アシスタント・ディレクターがそう叫ぶ中で私の胸の中ではある一つのメッセージがくっきりと浮かび上がっていた。---「世の中に偶然など一つも存在しない。私は賭けてもいい」。
テレビ・カメラの前では誰しもが「まな板の上の鯉」なのだ。私たちゲスト3人はただひたすらこのひと時の間に何かが起きないことを望み、懸命に答弁する。攻める側の田原総一朗は確かに勇ましく聞こえるが、しかし彼はあきらかに「事前に誰かに言われたこと」を執行するためにその場にいたように見えた。つまり彼もまた「まな板の上の鯉」であることには変わりがなかったのだ。
「それでは一体、本当の主はどこの誰であるのか」
容赦なく私たち3人を映し続けるテレビ・カメラの向こう側に広がる真っ暗な闇の中に、私は確かに巨大な「意図」を感じた。そこに確かに”在る何か”こそがこの世を動かす実態なのであり、道化師と化した私たち三人を料理する主人公なのである。いや、この暗闇の中にある「何か」は鵺(ぬえ)とでも呼んだ方が良いものなのかもしれない。そして私はこう思ったのである。
「この3人で、しかもこの順番で私たちは必ずまた出会うことになる。そう、必ず」
安倍晋三、石破茂、そして私。発言の順番は必ずこうであった。余りにも自然だが、しかし同時に余りも不自然すぎる並びであった。田原総一朗は私を執拗なまであげつらい、論難し続けた。私は苦笑を禁じえなかった。全くもって、この後にも先にもない「惨敗」だった。
番組が終わった後、スタジオを足早に去ろうとした私は舞台上の田原総一朗と目が合った。彼は右手を差し出し、無言で握手を求めてきた。何ともいえない笑みをその顔はたたえている。私はそこに、余裕ではなく、囚われ人であるからこそ、書かれたシナリオどおりに演じなければならない者の悲哀をむしろ感じた。そして爾後、彼と出会うことは(少なくともこれまでのところは)なかった。
「世の中に偶然など一つも存在しない。私は賭けてもいい」---これが世の真実なのだ。そしてそうである時、果たして私たち3人はどこで、どの様な形で再び出くわすことになるのだろうか。この「トリオ」を再び瞬時とはいえ結実させる「三重(水)素」は一体何であり、何時それは私たちの目の前に登場することになるのだろうか。
造られた「安倍一強」という”演出”を目の当たりにし、今、私はそのことばかりを考えている。「農村から都市へ攻めあがる」毛沢東戦略と「敗戦後まではまず何が何でも生き延び、その後、敗戦直後から一気に覇権を握る」という”ヨハンセン”たちの戦略とを併せ業で採用し始めたからこそ、そう想うのである。偶然ではなく必然が織りなす未来から降りかかって来る光の一点だけを見つめながら。
平成30年9月24日 東京・丸の内にて
原田 武夫記す
【※大事なお知らせ】
今回のブログの内容は、音声レポート「週刊・原田武夫」2024年6月28日号で詳しく解説しております!こちらからお買い求めください。