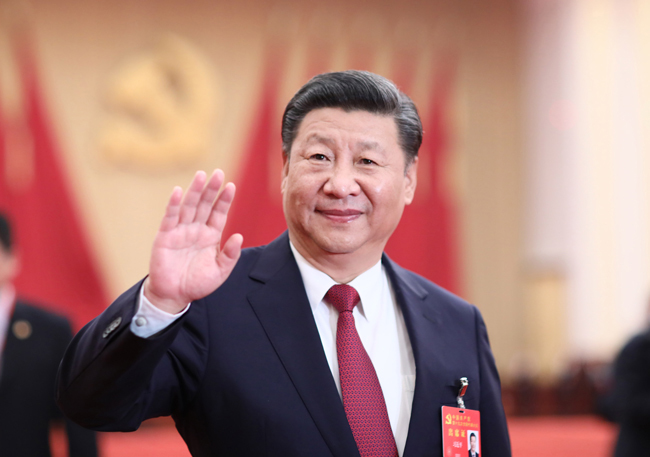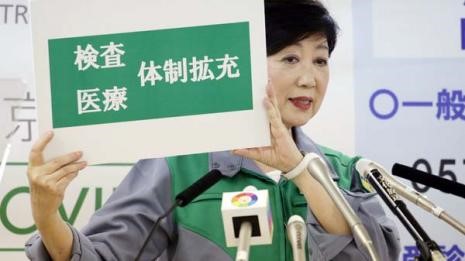「平成バブル」の残像。それでも私たちは未来に向けて生きていく (書評)

私・原田武夫は「漫画」を全く読まない。無論、嫌いだというわけではない。子供の頃には大いにハマり、何人かの作家の作品を買い漁ったものである。だが、大人になってからというもの、もっぱら活字の世界を生きるようになった。よほどのことが無い限り、図画の世界、あるいは「漫画」の世界には手を出さないのである。
だが、ここに来てとある作家の作品を読み漁っている。今回御紹介したい作品「毒親こじらせ家族」(竹書房)を発表した漫画家・松本耳子さんの作品群だ。
この作品で著者は優しい筆致なれど、壮絶な世界を描き出す。舞台は大阪だ。複数の「会社」を経営している(らしく)羽振りがやたらと良いものの、滅多に家には帰って来ず、無口な父親。そして掃除好きで整頓魔、さらには絵に描いたような「教育ママ」である母親。その二人の下で著者は幼い頃より冷静な眼差しを育まれていく。
物心がつくまで、それでも著者と妹・弟たちはこれらユニークだがそれなりに夫婦としては廻っている(ように子供心には見えた)両親の下で幸せに暮らしていた。時は「平成バブル」真っ盛りであった。明らかにヒステリックな教育ママであった「母親」の機嫌を損ねまいと、その着せ替え人形となりつつ、著者はひきつった笑顔を見せながら青春期を過ごし始める。
そこで訪れた「平成バブル崩壊」。父親はますます自宅へ帰って来なくなり、母親は身に着けていた宝石を一つ、そしてまた一つと手放していく。自宅にたまに戻って来る父親の車が外車から国産車となり、さらにはその大きさがどんどん小さくなっていくのを娘心の著者は決して見逃していなかった。そして「夫婦」の破綻、弟との離別。「家族」は崩壊した。
生きることに必死な母親は、次々と付き合う男性を変えていき、その度に家と苗字が変わっていく。惣菜屋で朝から晩まで働き、はじけ飛ぶ油がそんな母親の細腕に次々と火傷跡を残していくのを、著者は毎日の様に目の当りにした。そして時には、そんな母親が一人の「女」に戻り、見ず知らずの「男」とあられもない姿をさらしている姿すら目にしてしまうのだ。正に「生活のための闘争」、それが著者たちにとっての毎日だった。
一方、父親はというとようやくこの段階になってその素性と本性を顕にする。父親は何と「ヤクザ者」だったのである。しかも稀代の雀士であり、「神の手」の持ち主ですらあったのである。転落の人生を生き続ける父親は、何と自らの子供たちをも食い物にしていく。子供たちを出汁に使っては借金を重ね、あるいは子供たちからも借金をし、踏み倒していくのだ。必死にもがき続けた父親はやがて不治の病に冒される。最後の最後までトンデモな世界を生き続けた父親が息を引き取ると、今度はその遺骨を巡って叔母たちが争奪戦を繰り広げているのを著者は目の当りにする。そして母親の死。二人の「毒親」たちは、3人の子供たちの中でただ一人有名(芸術)大学を卒業した著者らを遺して、壮絶なフィナーレを迎えた。著者はやがて「漫画」の世界に自己表現の道を見つけていく―――。
何気ない出来事の連続かもしれない。あるいは(とりわけ関西では)「よくある出来事」なのかもしれない。だが私は松本耳子さんの作品を読む度に亡き父が遺した言葉をふと脳裏に思い浮かべるのである。
「武夫、一度持った家族を守り続けることほど大変なことはないぞ。あるいは人生とは、結局それのためにあると覚悟した方が良いかもしれない」
その父は我が国有数の保険会社に勤める絵に描いたようなエリート・サラリーマンだった。この言葉を私が聴いた頃、肩幅の大きな父は新調のスーツに身を包み、正に肩で風を切って歩いていたことをよく覚えている。青春期の私にとって、それは誇りであり、かつ同時に鏡でもあった。
だが、突然の不幸が私たちの家族を襲う。「平成バブル」で絶頂期であったこの有名保険会社の業績が「平成バブル崩壊」で一気に悪化。その責任の一端をとらされる形で、それまで会社人生一辺倒であった父親の役員昇進の道は閉ざされた。すっかり意気消沈した父親は生気を失い、不治の病に冒されてしまったのである。そして闘病すること4年。最後は文字どおり、朽ち果てるようにしてこの世を去って行った。
先ほどの松本耳子さんの「父親」と我が「父親」は無論全く違う世界に生きた男たちだ。だが「平成バブル」とその後突然続いた「平成バブル崩壊」の中で我らが父親たちはそれぞれのやり方で必死に生き抜こうとし、何とかして再起を図ろうとしたことは間違いない。子供たちである私たちに対し、時に全くもって無様な姿を見せながら、それでも這い上がろうと共に必死だったのである。そしてそうした「父親」たちとある意味対になり、これまた必死に生き抜こうとする「母親」たち。それらの姿に「生きること」そのものを見出し、時に当惑し、あるいは瞳に涙しながら暮らして来たこの20年。それが平成バブル不況で失われしこの25年余りの私たち「子供たち」の人生だったのである。
公式フェイスブックを拝見する限り、「毒親」たちの子・松本耳子さんは優しい御主人と元気なお子さんたちに囲まれ、平穏な日々の生活の中、創作活動に励まれているようだ。この本の中で描かれている騒乱の子供・娘時代とは余りにも違う生活である。「そうありたい」という意識をもって生活を守られているのだと思う。静かな、それでいて想念の世界においては豊穣な世界に囲まれた生活を。
そうした情景を垣間見ながら、私はふと、自らがなぜ作家になったのかを思い出した。父が不治の病に冒されていることをわざわざ告げにやって来てくれた兄が留学先のベルリンから帰国した後、私はハイデガーの「存在と時間(Sein und Zeit)」を手にしながら、イタリア・フィレンツェへと傷心の旅に出た。折しもクリスマス・イヴの当日であり、この見知らぬ街は騒然とした雰囲気に包まれており、そのことが私の心の痛みをますます深いものにしていった。
そして翌日。一転して静寂に包まれたフィレンツェの街を独り歩きながら、訪れたサンマルコ教会。そこで私は古びた机に座り、巨大な羊皮紙の聖書のページを一枚、そして一枚とめくりながら、聖なる言葉を耽読している聖職者たちの姿を目の当たりにしたのであった。すると私の脳裏に降りてきたのである。
「我が身体は潰えたとしても、我が言葉は本となればこの世から消えることはない。そうだ、言葉を綴っていくことにしよう。我が言葉を分身として世界に遺していくことにしよう」
爾来、多くの言葉を綴ってきたが、私は自らが吐く言葉を妨げる者を知らない性質であり、数多くの衝突を経てきたことも事実だ。しかし私にとって己の言葉を書き記し、伝えることは、私自身の「存在証明」なのであり、絶対に譲ることが出来ないことなのである。
私は今回御紹介した本の著者・松本耳子さんと未だ会ったことがない。しかしその作品は、その可憐な風貌からは想像がつかないくらい率直なものであり、人間の本性を抉り取るような世界を端的に描き出すものばかりである。筆舌に尽くしがたい壮絶なアップダウンを経てきただけに、「飾ってどうするか、たった一度きりの人生、丹精に、しかし率直に生きようではないか」という一貫したメッセージがそこには見て取ることが出来る。そしてその様に真っ直ぐに創作活動を続けていくことは、今な亡き「毒親」へのオマージュであり、そしてまた追憶でもあるのだ。
だが松本耳子さんは踏み止まってはいない。その作画構成は非常にテンポが良く、緻密に練られたものである。少しだけ読んでみようと手にとると、たちまち引き込まれ、各章のどういうわけか既に次の章の始まりでもあるという魔術にはまり込んでしまうことになる。精緻なドラマトゥルギーのプロフェッショナルだ。そのプロフェッショナル・松本耳子さんが「毒親」たちを超えて、次に如何なる新境地を私たちに向けて描き出していくのか。心から、楽しみでならない。
2015年7月5日
東京・仙石山にて
原田 武夫記す