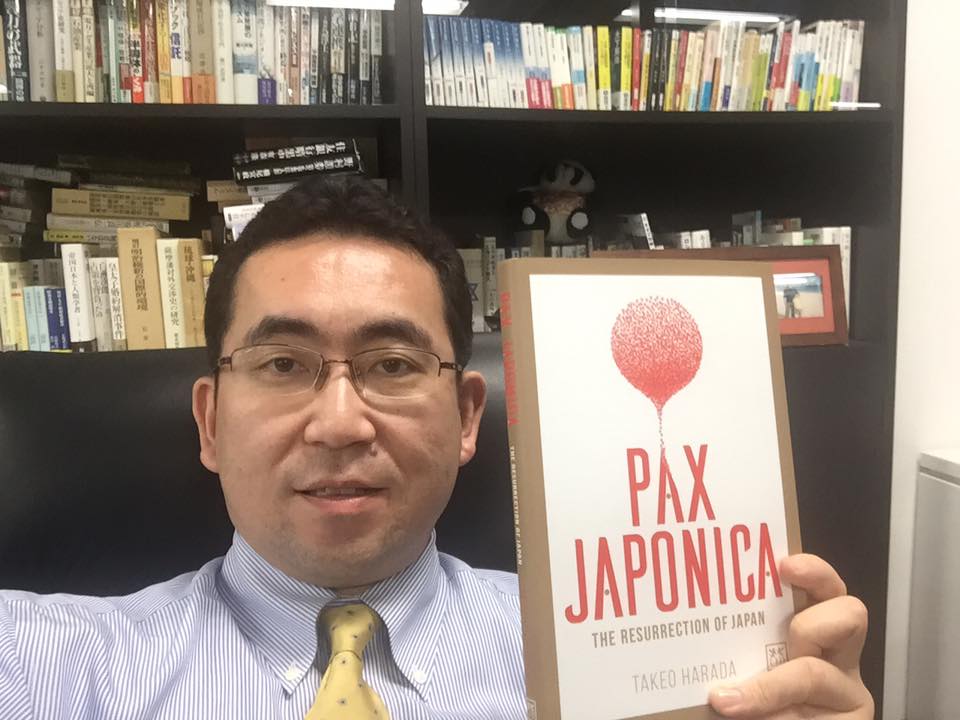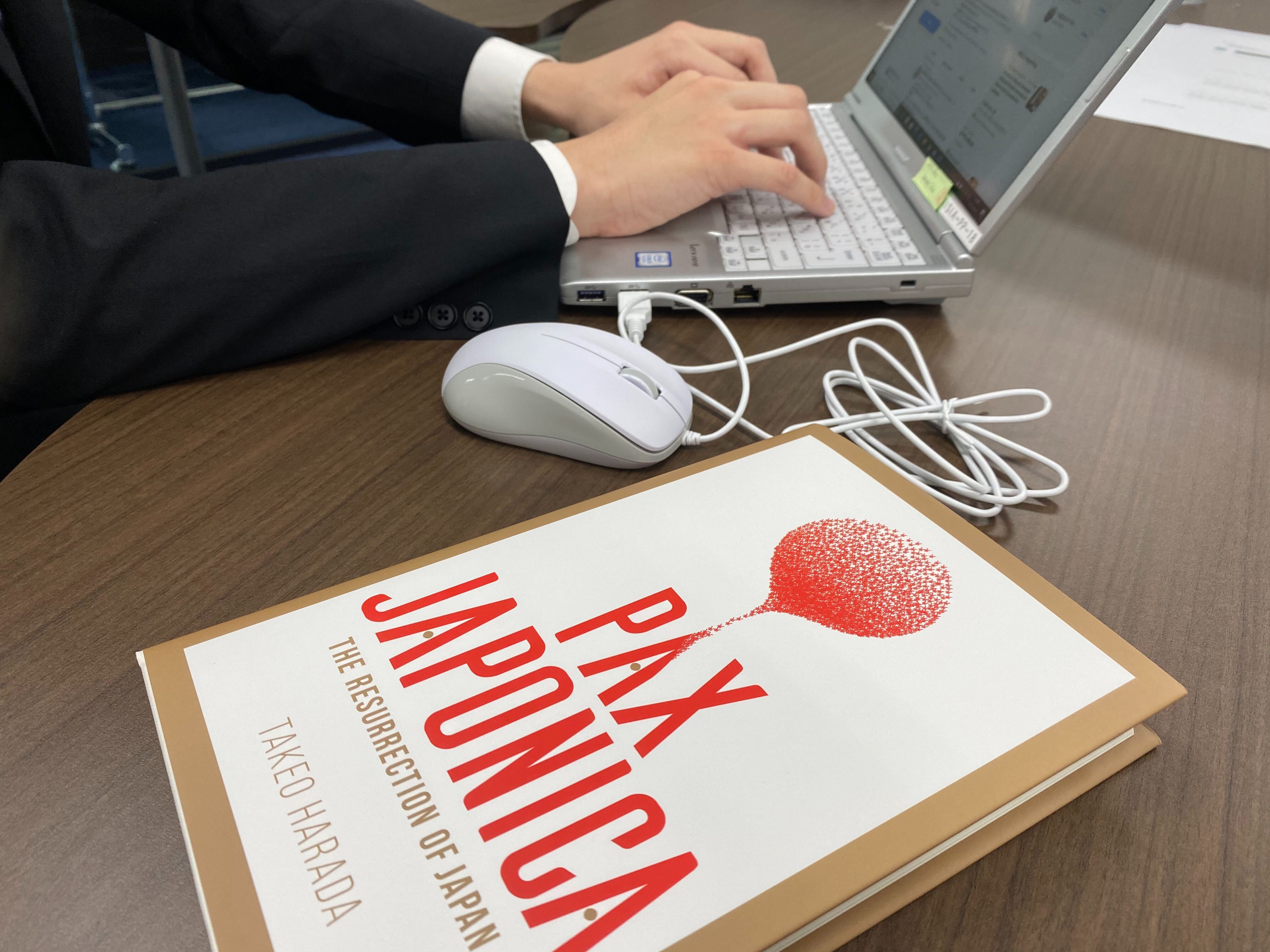「ペンス米副大統領の電撃訪朝」という悪夢。

「そして何も起こらなかった」というわけなのである。私たちの研究所があらかじめ分析を提示していたとおりであった。北朝鮮の金正恩は結局、核実験も、弾道ミサイルの発射も危惧されていた昨日(15日)に一切行わなかったのである。その代わりにワシントンD.C.からはこんなリークが飛び出してきたのである。
「核・ミサイルに関する交渉に応じるならば金正恩の体制転換は求めない」
これを読んで、やはりそうであったか、と納得した。要するに米国勢はここに来て、さんざん「軍事攻撃の可能性」を喧伝しつつ、実際には最終的に「外交交渉による妥結」、しかも二国間交渉による解決を希望していることをフロートさせ始めたというわけなのである。
無論、これは米朝間で何らの下ごしらえもなく行われていることではないということに留意する必要がある。こうしたリークを行う場合、対外情報工作機関(インテリジェンス)ルートでかなり緊密な接触を行い、事前に詰めているというのが米国勢のいつものやり方だからだ。すなわち今回は実際のところ、「砲弾が飛び交う」かの様に見せつつ、実際のところそれは人払いをしていたわけであって、ある瞬間に“どんでん返し”となって周囲が唖然とする中、米朝は「新たな同盟関係」に入ることを高らかに宣言するということになるというわけなのである。
そうした中でカギを握るのは「大統領」であるトランプではなく、「副大統領」であるペンスであることに注意を促しておきたい。全ての国には選挙によって選ばれることになっている「政体」勢力としてのリーダーと、いわばその国の根源的な階層に血統でつながっている「国体」勢力のリーダーがいる。実は現在のトランプ政権へ「国体」勢力として参画しているのは、米国勢が保有する簿外資産の最終的な管理権を担わされているペンス副大統領なのである。それに比べるとトランプ大統領は正にマリオネットなのであり、根源的な階層が描き出すシナリオを絶妙なやり方で演じ切っている存在であるに過ぎない。
そのペンス米副大統領がこのタイミングで東アジア歴訪を開始する。余りにも出来すぎた”演出“だとは思わないであろうか。しかも最初の訪問地は我が国ではなく、韓国・ソウルなのである。巨大な打撃艦隊が2つも洋上から護衛する中、在韓米軍の車両で38度線を越えればすぐそこは平壌なのである。夜陰に乗じて行うこのオペレーションの結果、翌朝、私たちは衝撃的な見出しを本邦各紙のトップで見つけることになる:
「ペンス米副大統領、電撃訪朝」
ペンス副大統領こそ、米国勢としての最終決定を下し、それを通じて世界秩序を転換させる権限を持っている。フランス勢を用いた資産運用を繰り返す北朝鮮勢はそのことを熟知しているはずだ。そしていよいよそうしたペンス副大統領が平壌から目と鼻の先にあるソウルにまでやって来ることとなり、「祝砲」ではないが、盛大にミサイルを打ち上げ、米朝交渉を行う意思を明確に示してきたというわけなのだ。そしてこれに米国勢も2つの打撃艦隊という異例の対応で応えたのである。
この交渉を通じて米朝は「同盟」関係に入ることになる。それはイコール、冷戦の激化を契機として「こうなった以上、アングロ・サクソンに我が国を守ってもらわなければ困る」と要求し、進駐軍の撤退を許さず、むしろ在日米軍という形で我が国の番犬とすることに成功した昭和天皇の戦略がいよいよ米国勢の手によって打ち破られることを意味しているのである。そして間髪入れずに米国勢は表向きは「日米同盟」を語りつつも、その”進化“を公然と要求し、これまでの警備料として法外な要求を次から次にし始めるのだ。これが「日米経済対話」などという緩いフレームワークとは別に、貿易を巡り日米二国間交渉の実施を求めていることの真意に他ならない。
こうなる結果、我が国は二つの選択肢のどちらかを選ぶことを強いられる。すなわち国防を自らで完全に担うか、あるいは米国勢がもはや頼りにならない以上、台湾勢や東南アジア勢といったジュニア・パートナーたちと共に全く新しい集団的安全保障の枠組みを創り上げか、のどちらかである。「もはや米国勢は私たち日本勢を守ってはくれない」という厳しい現実に慣れるまでかなりの時間が私たち自身の心理においてかかるに違いない。だがこれはもはや“現実”なのであって、後戻りすることは出来ないのである。
まずは今回の東アジア歴訪の中でペンス米副大統領が果たして「電撃訪朝」を行うか否かを見守ることにしたい。そして仮にこれが実現した場合、平壌からの帰途、東京に立ち寄るに違いないペンス米副大統領が”お土産“として日本人拉致被害者たちを連れ帰るかどうかにも注目しておきたい。なぜならば仮にこれらが本当に実現した場合、歴史はいよいよ次のページへと私たちをいざなうことになるからだ。もはや後戻りはできない形で。
2017年4月16日 東京・丸の内にて
原田 武夫記す
*さらに詳しい分析、とりわけマーケットへの影響と見通しを知りたい方はこちらをクリックしてください。14日にリリースした音声レポート「週刊・原田武夫」に飛びます。